気候変動影響について広く周知し、適応策の実践を促すために、研究機関と地域が連携
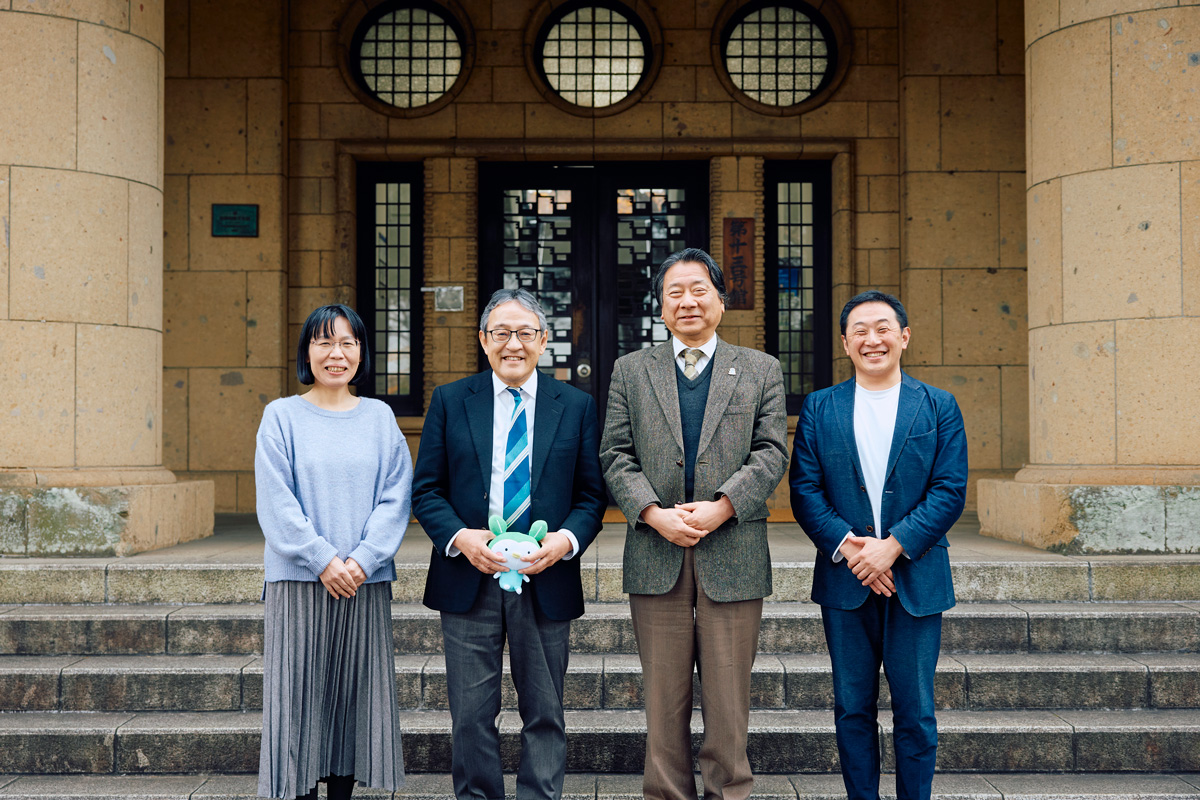
| 取材日 | 2024/12/25 |
|---|---|
| 対象 | 東京大学 先端科学技術研究センター ・教授 中村尚 ・特任准教授 飯田誠 国立環境研究所 気候変動適応センター 気候変動影響評価研究室 ・主任研究員 石崎紀子 山口県気候変動適応センター ・センター長 調 恒明 |
過去の気象データを整備し、将来予測に繋げる『ClimCORE』
東京大学先端科学技術研究センター(以下:先端研)は、国立環境研究所 気候変動適応センターとどのような連携をとっていますか?
石崎さん:私はもともと、地形が気候にどのような影響を及ぼしているかという解析をしていましたが、現在はそのメカニズムだけでなく、地域の気候変動適応策を検討するために用いられる、将来の気候シナリオの開発にも取り組んでいます。
気候シナリオはA-PLATに搭載して将来の地域の気候の変化を調べたり、気候変動が健康や農業などに及ぼす影響を調べたりするためのデータとして、広く使っていただけるよう提供しているのですが、現在の気候シナリオにはいくつか課題があります。そのひとつが、シナリオ開発時に使用する地上観測データが均質でなく分布にばらつきがあることです。
日本では、気象庁による観測網が密に整備されていますが、とりわけ山岳地域に観測地点が少ないという問題があります。多くの人は平野部に住んでいるのでさほど問題ではないと思われがちですが、山岳域のスキーや紅葉狩りといったレジャー、高山植物、さらに貴重な水資源である雪など、恩恵を受けている部分が多くあり重要です。
観測地点の抜けをどうするか、という問題にあたり、現在先端研と共同で進めているClimCOREプロジェクトの中で開発している領域再解析データを取り込み、観測データと再解析データをうまく融合することで、過去や将来の気候シナリオをより高度化しようという取り組みをおこなっています。

ClimCOREとは、どのようなものですか?背景も含めて教えてください。
中村先生:ClimCOREは、「地域気象データと先端学術による戦略的社会共創拠点」(Climate change actions with CO-creation powered by Regional weather information and E-technology)の略で、大学研究機関、企業・自治体などが参画し、「日本域気象再解析」を軸とした気象データを戦略的かつ有機的に利活用可能とする体制を構築するプロジェクトのことです。
日本列島は海に囲まれていて、かつ高い山もあり、とても複雑な地形をしています。そして気象や気候などは、局所的に地形の影響を受けています。
温暖化の対策を実施するうえで、過去から現在にかけて大気や海の状態の変遷があったかを理解しないと「いま」を知ることはできません。なぜこのような異常気象になったのか、地域によってどのような違いがあるのかを理解し、今後温暖化が進行するとどういう状況になりうるのかを考える。そうすることで、有効な適応策を立てることができます。
また、緩和策として有効な再生可能エネルギーも、風や日射など、気象の条件に強く依存します。各地域のポテンシャルを知ることで、どこにどのような施設を作って、どう効率的に運用していくかを考えることができます。これも、過去の気象や気候の状況がわからないとできないことです。
しかし現在主に利用されているアメダスは、世界に誇れるシステムではあるものの、先ほど石崎さんがおっしゃったように山岳地帯に観測地点が少ないなど、地域の特性を正確に把握するのは困難です。地上観測であるがゆえに、海上のデータも観測することができません。これまで災害をもたらした豪雨や台風について、予測再現実験ができないというデメリットがあります。
また、さまざまな分野の人がオンラインで手軽にデータをとることができるプラットフォームもありませんでした。そこで、過去から現在に至るまでの地域の気象データをきちんと整備し、将来予測に繋げるための基盤を整備し、広くみなさんに使っていただけるようなオンラインプラットフォームを作ろうということで始まったのがClimCOREプロジェクトです。
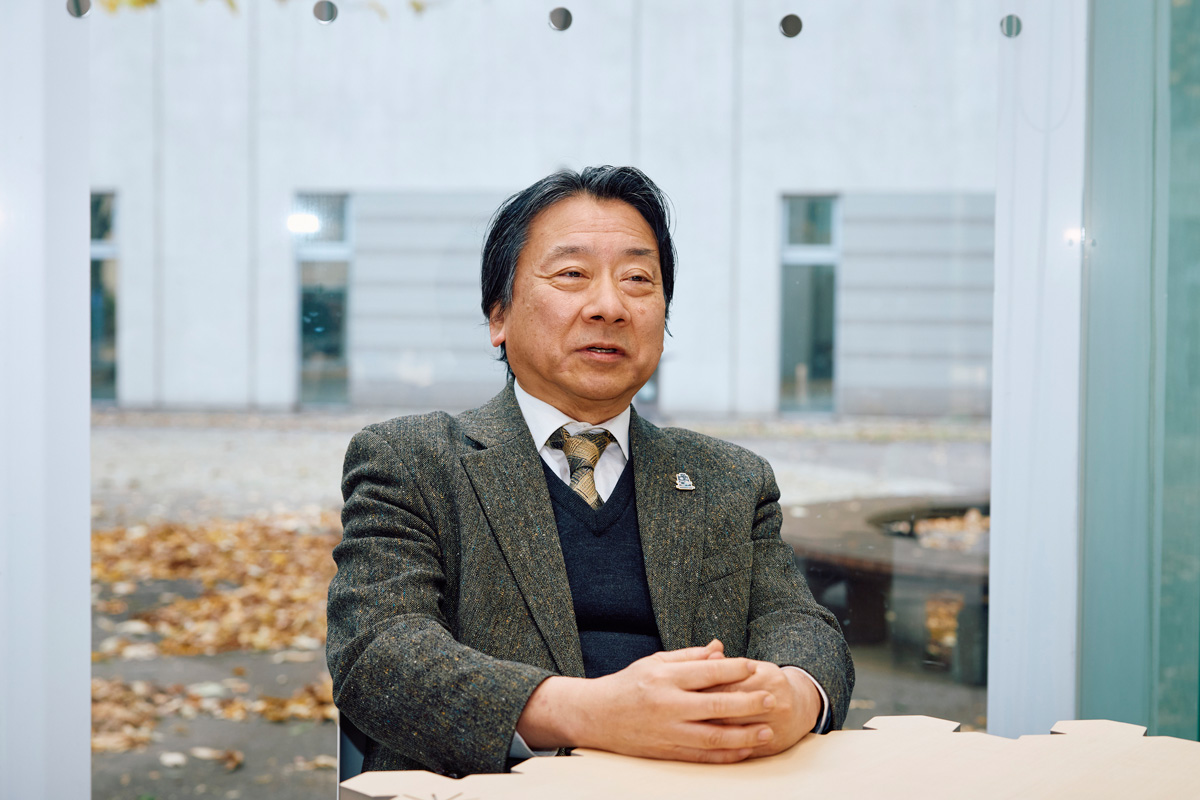
地域とともに、気候変動を学ぶ若者の育成に力を入れる先端研
先端研は山口県気候変動適応センターとも人材育成について連携していると伺っていますが、詳しくお話しいただけますか?
調さん:令和4年8月に、山口県と先端研は『山口県新たな時代の人づくりに関する連携協定』を締結しました。この連携協定に基づき、「ふるさと山口への誇りと愛着を高める」「新たな人づくりの推進体制を築く」などをテーマとして、県関係部局がセミナーなどを開催し、様々な分野で将来の教育や人材育成についての取組を推進しています。
その枠組みの中で、気候変動の最先端の研究をされている先端研と山口県気候変動適応センターで連携したという経緯です。2024年2月には『気候変動を学ぶステップアップセミナー』を開催し、中村先生、飯田先生を講師にお招きし、地域の活動団体の方や高校生の環境活動の発表や、グラフィックレコーディングなどを用いたパネルディスカッションを行いました。
セミナー後のアンケートでも大変な反響があり、非常に有意義なセミナーであったと思います。今後も若い人たちに気候変動について正確に伝えつつ、定着させることに取り組んでいきたいと思っています。

実際にセミナーに参加されてみていかがでしたか?
中村先生:最初に、特別講演として、いま世界がどのような状況なのか、日本ではどんな異常気象が起きていて、温暖化の影響がどのくらいあるのかということも含めてご紹介しました。2023年の夏は記録的に暑かったので、温暖化を自分事として捉える題材になりました。日本に猛暑をもたらす、たとえばジェット気流の蛇行はどのような仕組みで起こるのか、日本近海の海洋熱波と呼ばれる温度の高い海水が、記録的猛暑にどのように輪をかけたのかといった内容を紹介し、気候の揺らぎが重なって災害や異常気象が起きているということを、しっかりとご理解いただきました。
そして高校生や民間団体の方に、気候変動について自分たちにできること、地元でできることなど、具体的な取り組みについて発表いただき、みなさんしっかりと意識を持っていることがよくわかりました。相互通行でお互いに活発なやり取りができた、非常に印象に残るイベントでしたね。
飯田先生:私はさまざまな自治体でディスカッションをする機会がありますが、とかく聞くことに必死になってしまう子どもたちが多いなかで、若い子たちが自分の意見や思いを出してくれたのはすごくおもしろかったですね。それはやはり、山口県が気候変動対策についていろいろな取り組みを進められているからではないかと思います。ぜひ引き続き続けていただき、機会があればほかの自治体との連携もできたらと思いました。

産学官が連携し、気候変動対策を実践に移すための舵取りを
現在認識しているもの以外の気候変動影響がこれから出てくる可能性もありますが、そのようななか、大学研究機関はどうあるべきとお考えですか?
中村先生:効果的な適応策や緩和策を実施するためには、大学や研究機関がリードしていく必要があります。産学官が連携する際には、学が産と官の間に入って社会実装に繋げるような取り組みがますます重要になると思います。そのひとつの試金石として、ClimCOREのプロジェクトを成功させなければいけないという責任を感じています。
石崎さん:産学官の連携は、科学的知見に基づいて気候変動対策を推進するために絶対に必要だと思います。現在、各地に地域気候変動適応センターが設立され、適応計画が策定されてきていますが、まだ起こっていない影響の認知や適応策の検討はなかなか難しいということをよく聞きます。その中で、各地の取り組みを見ると、高校生や大学生など若い人たちを巻き込んだ活動が、社会を動かす最初の一歩としてうまくいっている印象があります。先ほどおっしゃった山口県の事例のように、教育的な、人材育成という意味での若者を巻き込んだ取り組みがますます重要になっていくと思いますし、それが理想的な形だと思います。
飯田先生:私たちの研究でも「二酸化炭素の排出はどうやったら減らせるか」といった議論が多いのですが、おふたりがおっしゃるように「実態を理解したうえで、どう自分たちが取り組んでいくか」というところまで届かないことが、教育上多いのです。これは難しいところでもありますので、一緒に考えていきたいですね。「気温が上がる」という事実から、「実際に自分たちの生活はどうなるのか?」という具体像を議論できるようになることを期待しています。
調さん:地方自治体の立場からもそこは大変重要と捉えていますので、山口県でも気候変動適応策の推進のために産学官で連携し、若者を巻き込んだ取り組みを継続的にやっていく必要があると考えています。

今後、より力を入れていきたいことについて教えてください。
調さん:2021年に山口県気候変動適応センターを設置し、国立環境研究所の助言を受けながら、気候変動を自分ごととして捉えるためのWebアプリの開発や関係機関と連携したセミナーの開催など、さまざまな取組を実施し、センターの認知度も向上してきています。気候変動の取組を紹介する講師として企業に呼ばれるなどのつながりもできているので、多様な機関と連携を強化し、取り組みをアップデートしつつ、新しいことにも取り組んでいけたらと思っています。
中村先生:山口県とも一緒に取り組んでいますが、人材育成は研究機関の重要な使命です。玉石混合の情報のなかから正しいものをきちんと選び出して、自分で考えたうえで最新のIT・AI技術を活用して、優れた成果を出す。そういった研究の進め方を若い人に身につけていただき、持続可能な社会の実現や問題解決に活かしていってもらいたいです。
石崎さん:ClimCOREの領域再解析データを使い、気候シナリオを高度化することは今後も継続して実施していきます。気候シナリオの高度化による将来予測の科学的な確認・検証も大事ですが、気候データを使ったことのない人にも気軽に使っていただくためにはどう工夫したらいいかといったことも考えながら進めたいと思っています。
飯田先生:私たちは引き続きClimCOREのなかで、データに基づいてきちんと理解しつつ、そこで自分たちがどう行動するのか、提供できる技術は何かということを考えていきます。向こう1〜2年で使える技術はないかもしれませんが、10年先を見たときに「あのとき研究をしておいてもらってよかった」と思ってもらえるような研究をしたいですね。目先の利益だけではなく、将来の備えに重点が置かれた研究開発ができるといいなと思います。

この記事は2024年12月25日の取材に基づいています。
(2025年5月20日掲載)