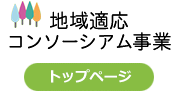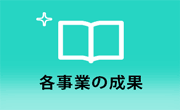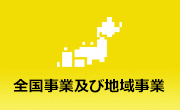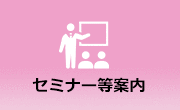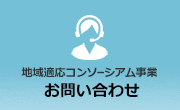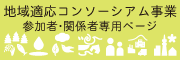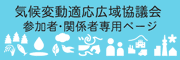気候変動による森林生態系への影響に係る影響評価
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 調査種別 | |
| 分野 | 自然生態系 |
| ダウンロード | |
| 地図データ |
概要
背景・目的
気候変動による森林分布やその周辺の生態系への影響が懸念されている。特に樹木の移動速度は動物と比較して著しく遅く、気候の急激な変化によって希少な樹種やその周辺の生態系の構成種が絶滅の危機に陥る可能性も指摘されている。一方で、南方種であるマダケ等(産業管理外来種)の竹林が、気温の上昇によって分布可能域を拡大し、里山の生態系・生物多様性に著しい悪影響を与える可能性も高まっており、全国的な課題となっている。そのため本業務では、気候変動が森林生態系に及ぼす影響について、最新の影響評価モデルや気候シナリオを活用して影響予測を実施した。
実施体制
| 本調査の実施者 | 森林総合研究所、国立環境研究所 |
|---|
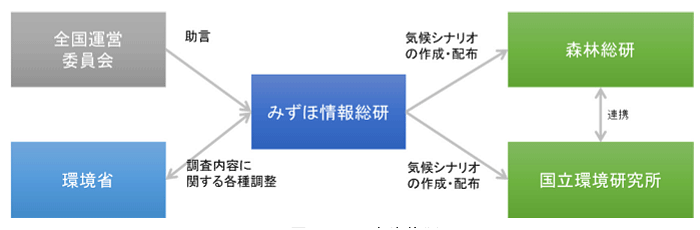
実施スケジュール(実績)
実施スケジュールを以下に示す。
- 気候変動影響予測を行うための基礎データの収集整備。
- 気候変動によるアカガシ、シラビソ、ハイマツ、ブナの潜在生育域への影響及び竹林の拡大についての将来予測と予測マップの作成。
- 気候変動下の将来のマツ枯れ危険域予測について、全国レベルの予測マップの作成の試行。
- 気候変動による生物の生育環境への影響予測に関する、全国規模の影響予測、予測マップ作成、および実装のための検討。
- モデル地域とその地域特有の自然生態系を対象とした適応策の効果的・継続的な実施のための、定量的なモニタリングとモデリングの一体的運用に資する手法の検討を、佐賀県の樫原湿原を対象に試行。
- 作成した将来予測マップ等の成果物の公表に関して国立環境研究所の協力を仰ぎ、気候変動適応情報プラットフォームへの掲載を試行。
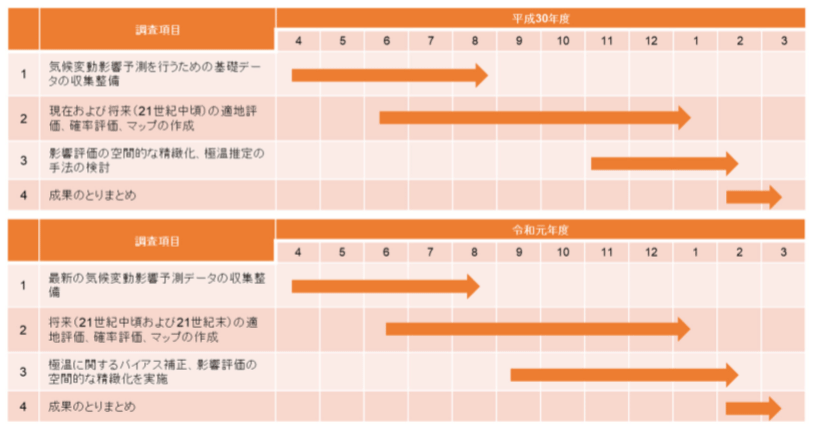
気候シナリオ基本情報
影響評価に用いた気候シナリオ、気候パラメータの詳細を下記の表 6.1-2、表 6.1-3、表 6.1-4に示す。
| 項目 | アカガシ、ブナ、シラビソ、ハイマツ | 竹林 |
|---|---|---|
| 気候シナリオ名 | 農環研データセット by SI-CAT | |
| 気候モデル | MIROC5、MRI-CGCM3 | |
| 気候パラメータ | 暖かさの指数、 最寒月の最低気温、 冬期(11月~4月)の降水量 夏期(5月~9月)の降水量 |
最も気温の低い四半期の平均気温と降水量 最も気温の高い四半期の平均気温と降水量 |
| 排出シナリオ | RCP2.6、RCP8.5 | |
| 予測期間 | 21世紀中頃、21世紀末 | |
| バイアス補正の有無 | 無し | |
| 項目 | マツ枯れ |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | 農環研データセット by SI-CAT |
| 気候モデル | MIROC5、MRI-CGCM3 |
| 気候パラメータ | 年平均気温、平均日気温幅、等温性、年気温幅、 最も降水量の多い四半期の平均気温、 最も降水量の少ない四半期の平均気温、 年降水量、降水量の季節性、最も気温の低い四半期の降水量 |
| 排出シナリオ | RCP2.6、RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀中頃、21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 無し |
| 項目 | 気候変動の速度(Velocity of Climate Change:VoCC) |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | 農環研データセット by SI-CAT |
| 気候モデル | MIROC5、MRI-CGCM3 |
| 気候パラメータ | 年平均気温 |
| 排出シナリオ | RCP2.6、RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀中頃、21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 無し |
気候変動影響予測結果の概要
気候変動によるアカガシ、シラビソ、ハイマツ、ブナの潜在生育域7) への影響
1)アカガシ
暖温帯性の常緑広葉樹であるアカガシの潜在生育域は、温暖化により拡大する(図 6.1-2)。潜在生育域の変化に気候モデルやRCPによる大きな差はないが、MIROC5のRCP8.5において潜在生育域が最も広がる予測となった。アカガシの分布北限や上限の制限要因として、生育期の気温や冬季の寒さが知られている。つまり、アカガシの潜在生育域が拡大した要因としては、温暖化により冬季の寒さが緩和されることが寄与したと考えられる。しかし、アカガシを含む常緑広葉樹林が生育する場所と都市や農地の場所は重なっており、森林の分断化が進んでいる。このため、実際の分布拡大は制限される可能性が高いこと、さらに種子散布による分布移動速度が遅いことなどから、予測が示すほどの急激な拡大はないと考えられる。
2) ブナ
冷温帯性の落葉広葉樹であるブナの潜在生育域は、温暖化により縮小し、西日本の潜在生育域の縮小が顕著である(図 6.1-3)。特に、現在でも山頂部に孤立的に分布する脊振山地(福岡県と佐賀県の県境)やブナ分布南限の高隈山(鹿児島県)は、RCP2.6で大幅に縮小し、RCP8.5ではいずれの気候モデルでも地域内から潜在生育域が消失する。一方、西日本地域においても、九州山地、中国山地、四国山地の主稜線部が潜在生育域として残る可能性があるため、各地域におけるブナの逃避地として重要な場所と考えられる。
3)シラビソ
亜高山帯性の針葉樹であるシラビソの潜在生育域は、温暖化により縮小する(図 6.1-4)。特に、シラビソの分布南限域に当たる四国山地や紀伊半島の大峰山系では、RCP2.6において潜在生育域がわずかに残存するが、RCP8.5では消失すると予測された。同様に、東北地方の山地においても、潜在生育域の縮小が予測された。一方、中部山岳域では、RCP8.5においても潜在生育域は残存すると予測された。
4)ハイマツ
高山帯・寒帯性の針葉樹であるハイマツの潜在生育域は、温暖化により全国的に縮小すると予測された(図 6.1-5)。特に東北地方の山塊に孤立的に分布する個体群において潜在生育域の縮小が予測された。つまり、ハイマツは温暖化に対して脆弱な種類であると言える。特に、ハイマツの伸長成長、高山帯への新たな植物種の侵入などに対し、注視する必要があることが示唆された。
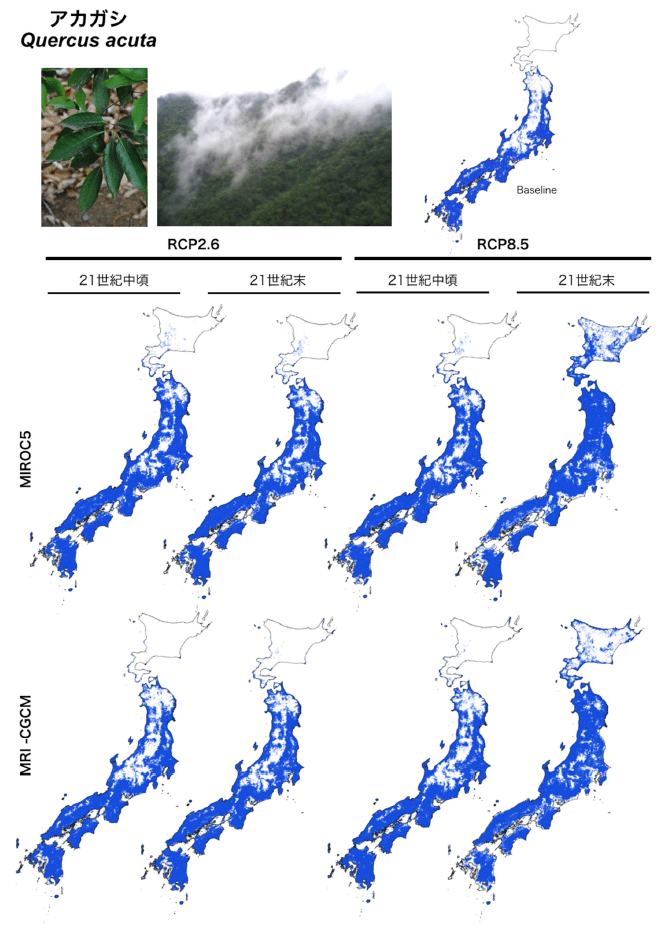
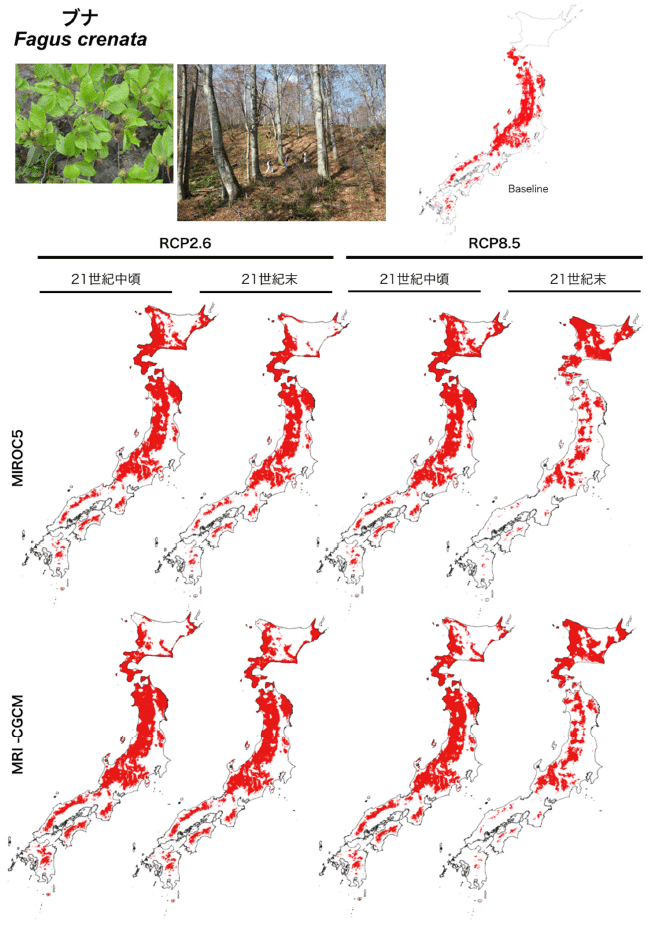
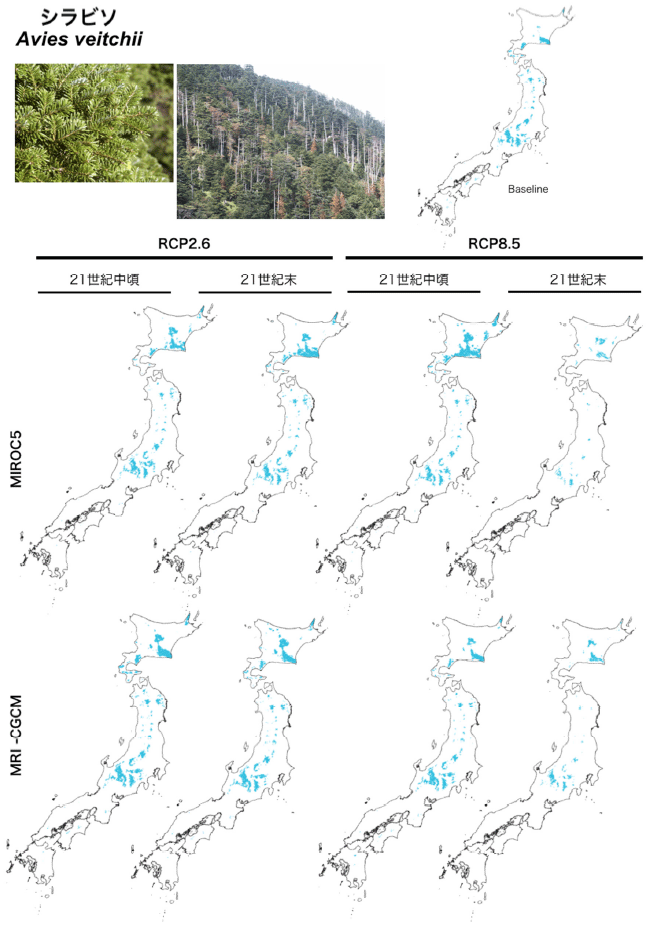
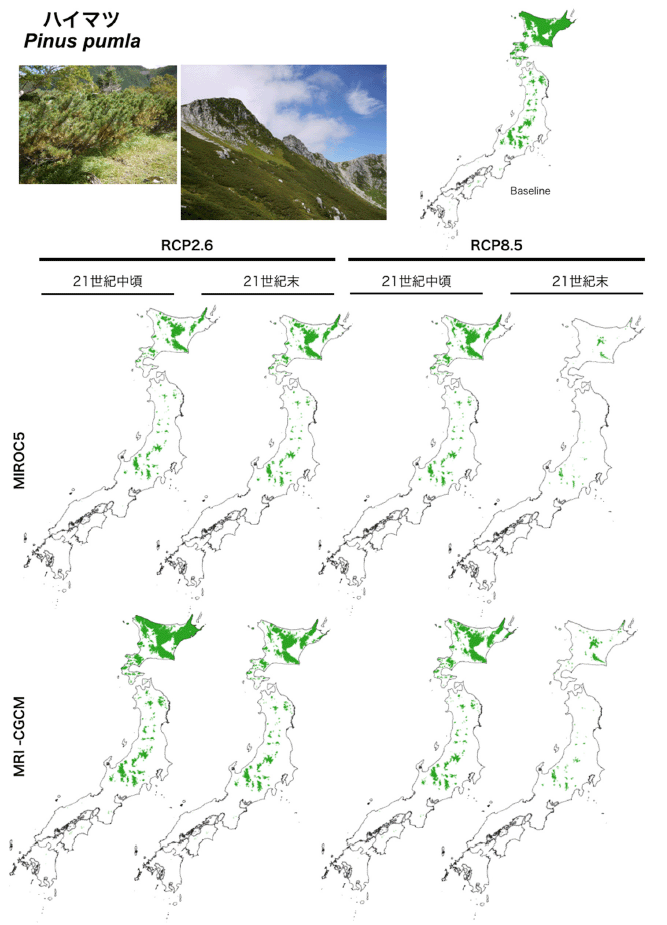
気候変動にともなう竹林の潜在分布域の予測
現在の気候条件下では、西日本の一部の高標高域以外および東日本の低地が、竹林の分布確率8) の高い地域として判定された。将来は、いずれの気候モデルにおいても、分布確率の高い地域はより高緯度、高標高地域に広がることが予測された(図 6.1-6、図 6.1-7)。東北地方や本州中部の山岳域では、現在は分布確率が0.4を超える地域は広くないが、RCP2.6の21世紀末には、低標高域を中心に分布確率が0.4を超える地域が広がることが予測された。RCP8.5の21世紀末では、北海道の低地でも竹林の分布確率が0.2を超える地域がみとめられた。
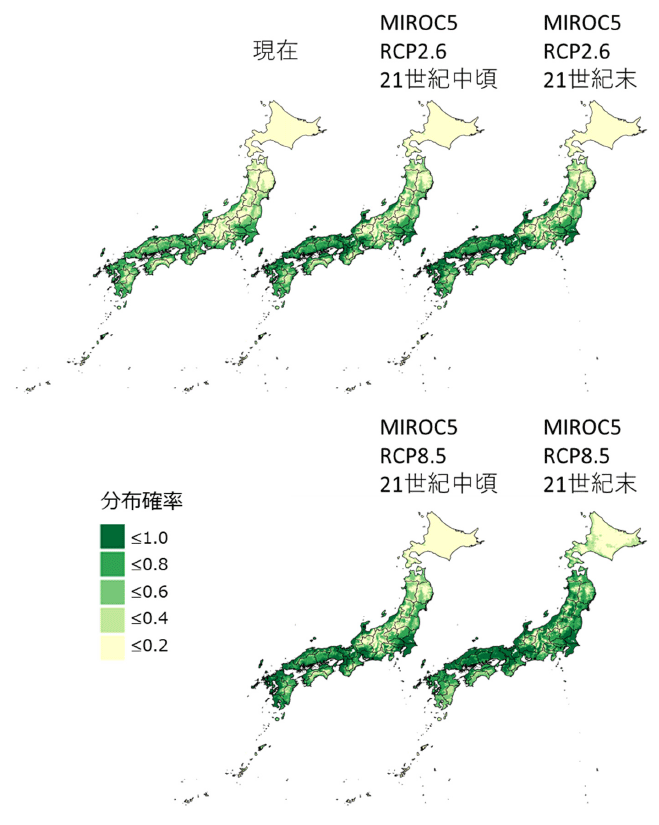
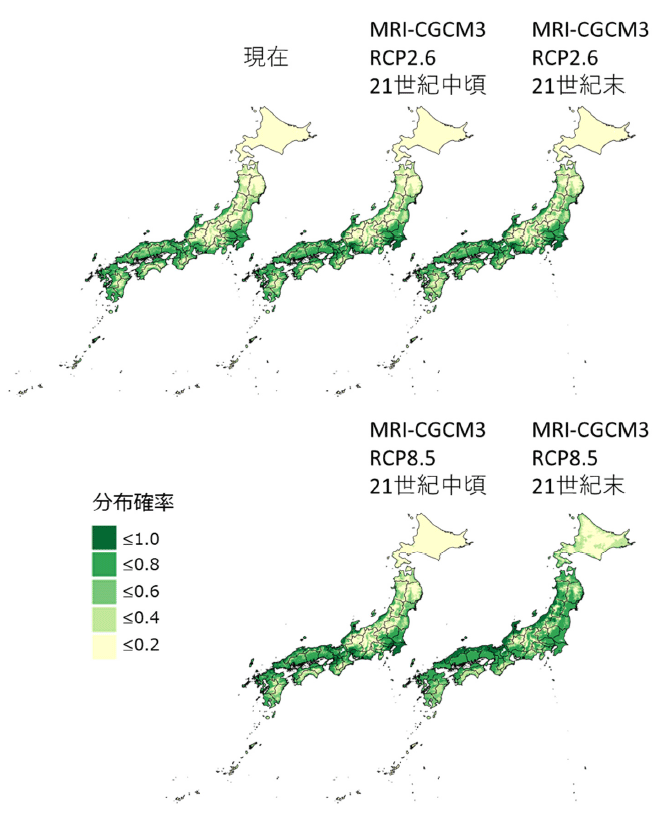
気候変動による全国レベルのマツ枯れ危険予測
モデルの予測値を5段階の危険度に区分し(表 6.1-5)、現在および将来の気候条件下でのマツ枯れ危険域予測マップを作成した(図 6.1-9, 図 6.1-9)。現在気候下では、西日本の高標高域以外、および東日本、北海道の低標高域が危険度の高い地域として判定された。気候変動にともなって、危険度5の地域は高標高域、高緯度地域に拡大する傾向がみられたが、拡大の度合いは気候シナリオによって異なった。例えばMIROC5モデルのRCP8.5の21世紀末の条件下では、本州及び北海道の一部の高標高域を除いた全域が、マツ枯れ発生危険度の高い地域として判定された。
| 危険度 | 詳細 |
|---|---|
| 5 | マツ枯れが大発生する可能性が高い地域 |
| 4 | マツ枯れが大発生する可能性がある地域 |
| 3 | マツ枯れが発生する可能性がある地域 |
| 2 | リスクは低いものの、マツ枯れが発生する可能性がある地域 |
| 1 | マツ枯れの発生する可能性が低い地域 |
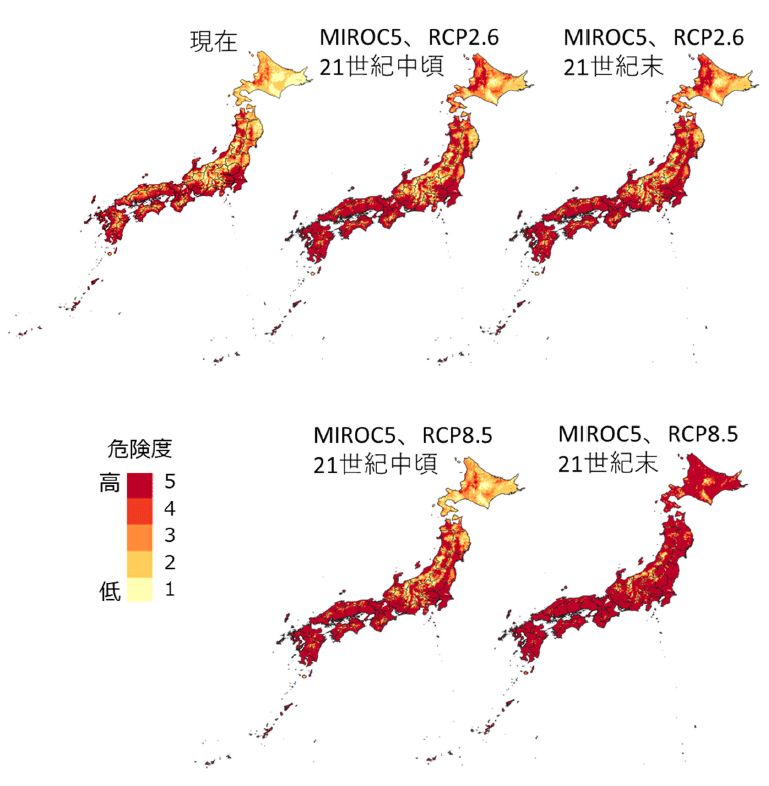
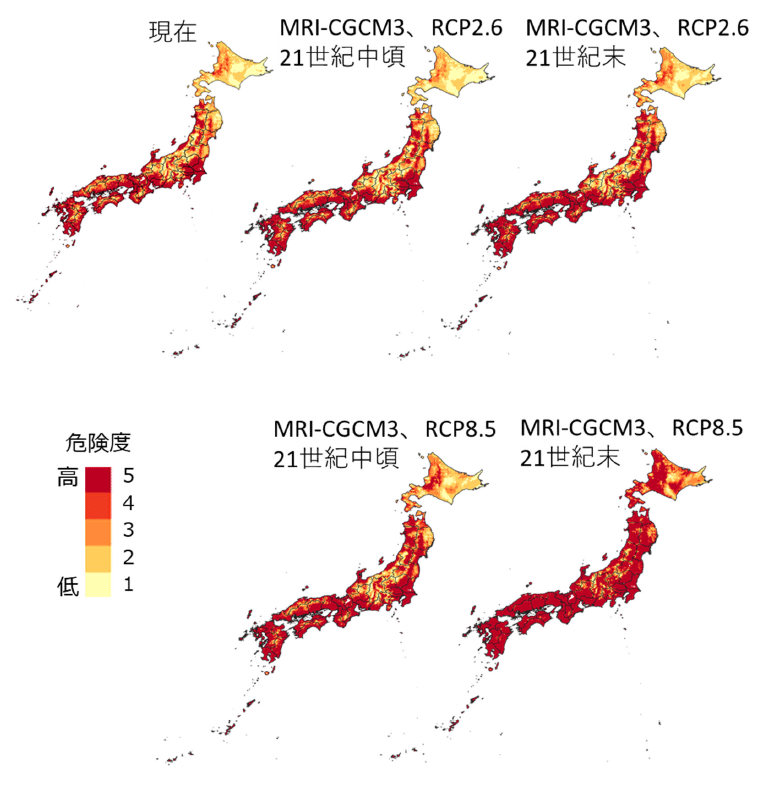
気候変動による生物の生育環境に関する全国規模の影響予測
気候変動による生物の生育環境に関する影響予測について、気候変動の速度(Velocity of Climate Change: VoCC)を計算した。その結果、MRI-CGCM3、RCP2.6、21世紀中頃のケースでは、全国のほとんどの地域が100m/年を下回るVoCCであるのに対して、RCP8.5、21世紀末のケースでは、MIROC5とMRI-CGCM3いずれの気候モデルとも多くの平野部で100m/年を超え、さらに北海道中央部の大雪山地では、他に逃避場所がなくなってしまう面積が広範囲にわたることが示された(図 6.1-10、図 6.1-11、表 6.1-6)。
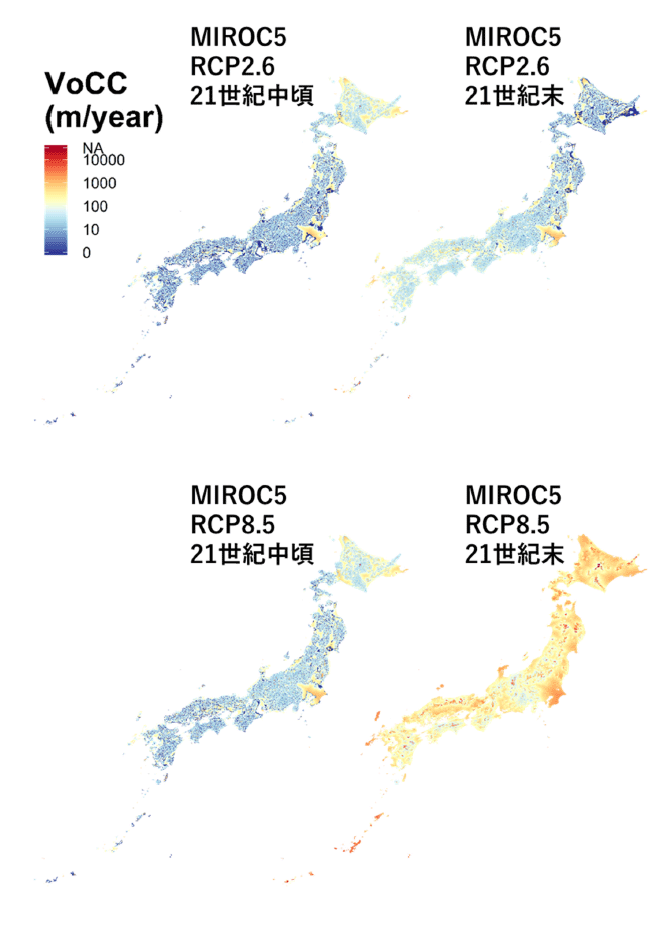
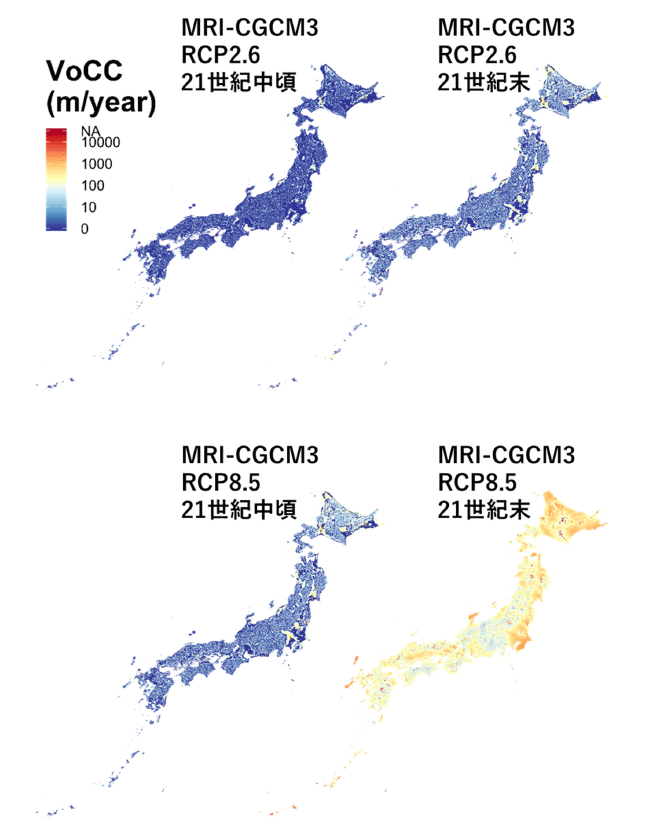
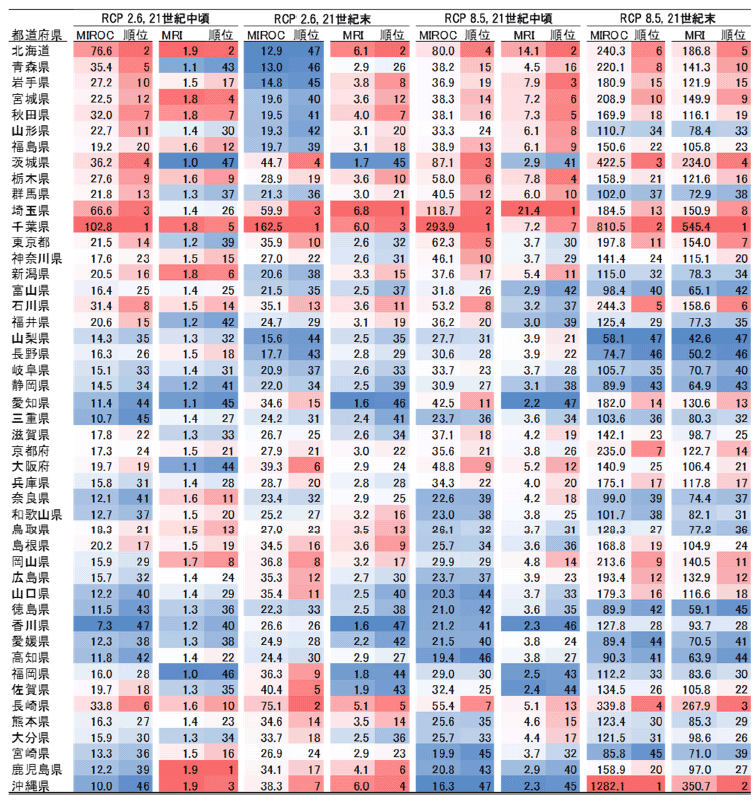
樫原湿原におけるモニタリング - モデリングの一体的な運用手法の検討
佐賀県の樫原湿原を対象に、地域の自然生態系における具体的な適応策の運用を想定した、モニタリングとモデリングの一体的な運用手法の検討を行った(図 6.1-12)。
効率的かつ省力的なモニタリングの運用を目的として、ドローン(以下、UAV)および機械学習技術を用いた対象植生の自動抽出技術を検討し、樫原湿原の保全上重要な低茎湿性群落の空間分布をドローン空撮画像から抽出できる可能性を示した。また、低茎湿性群落を対象に温暖化による影響予測情報の基盤となる分布予測モデルを構築し、分布規定要因を定量的に明らかにし、将来気候シナリオに基づく将来予測を試行した。分布を規定する要因の重要度は、DSM、次いで凹凸度、傾斜、平均年冠水日数、平均夏期冠水日数、平均冬期冠水日数の順だった。構築したモデルを用いて、現在の潜在生育域を予測したところ、モデルの正答率はAUC = 0.86と高かった。また、将来気候シナリオを用いた将来予測では、現在の潜在生育域の一部で縮小する可能性が示唆された。さらに、想定される適応策を整理し、樫原湿原におけるモニタリング - モデリングに基づく適応策の運用のあり方について検討した。
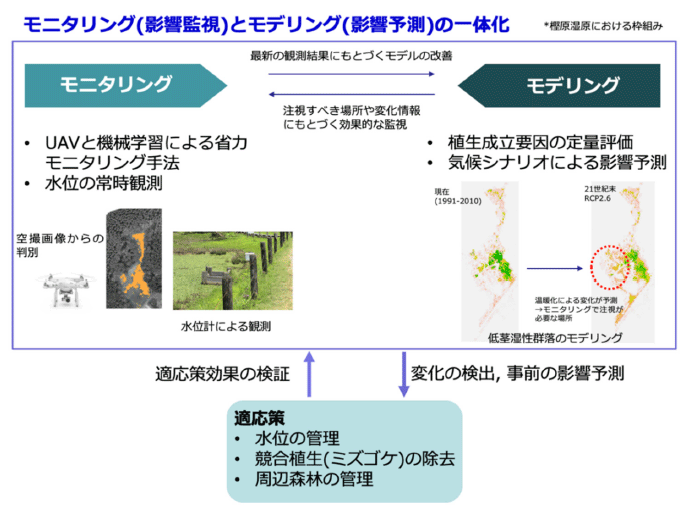
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
本調査では、気候変動によるアカガシ、シラビソ、ハイマツ、ブナの潜在生育域への影響、竹林の拡大への影響、マツ枯れリスク域への影響、生物の生育環境への影響を対象とした。
また、定量的なモニタリングとモデリングの一体的な運用に資する手法についても検討した。
本調査の将来予測の対象外とした事項
生物の分布には、気候以外にも、立地条件や人為影響など、様々な生物的、非生物的要因が影響しうる。本調査では、生物の気候的な分布可能域が気候変動によってどのように変化するかを評価しており、土壌の違いや、他の生物群との競争関係、人為などの気候以外の要因の影響は考慮していないことに留意が必要である。
また、実際の生物の分布拡大速度は、森林などの生育に適した土地被覆の分断化や、種子散布による分布移動速度などにも影響を受ける。そのため、予測が示すほどの急激な分布拡大は必ずしも起きないことにも注意が必要である。
気候変動の速度(VoCC)は、扱う気候パラメータによっては、気候モデルの予測の不確実性が結果に反映されやすいことに注意が必要である。特に、島嶼部や地形が急峻な地域では、気候の変化がある一定の閾値を超えると移動先の候補が近くになくなるため、気候モデル間で結果のばらつきが大きくなる可能性があることにも留意が必要である。
その他、成果を活用する上での制限事項
上記6.1.6.2を参照。
適応オプション
適応オプションの種類やその詳細について、表6.1-5に記す。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面(知見/経験/データなど) | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 自然保護区等の配置見直し・生物の逃避地の保全 | ● | 普及が進んでいない | 法律や土地利用の見直しが必要 | △ | △ | △ | △ | 長期 | 中 | ||
| 拡散経路の確保や拡散補助 | ● | - | 拡散補助手法の検討は今後の課題である | △ | △ | △ | ◎ | 長期 | 中 | ||
| ニホンジカによる食害影響の緩和 | ● | ● | ● | 普及が進んでいない | シカによる植生被害は全国的な問題である | ◎ | △ | △ | △ | 長期 | 中 |
| VoCCを指標とした高山帯の野生動植物の生息域外保全 | ● | 普及が進んでいない | 高山帯に生息する生物は温暖化した場合に逃げ場がなくなってしまう可能性がある | △ | △ | △ | △ | 長期 | 中 | ||
| VoCCを指標とした適応策の検討に資する、情報共有ツールの開発 | ● | VoCCを指標とした情報共有ツールの開発には至っていない | △ | △ | △ | △ | N/A | 低 | |||
| マツ材線虫病被害拡散前の伐採と利用 | ● | ● | ● | 普及が進んでいない | 拡散前の伐採よりも、拡散後の駆除が多いと思われる | ◎ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 中 |
| マツ材線虫病抵抗性マツの開発と利用 | ● | ● | ● | 普及が進んでいる | 林木育種センターがマツノザイセンチュウ抵抗性品種として公表している | △ | △ | △ | ◎ | 長期 | 中 |
| 竹林の適切な管理と利用を促進し、安易な新規植栽を避ける | ● | ● | ● | - | 特に西日本では竹林の拡大が顕著である | △ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 中 |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| 自然保護区等の配置見直し・生物の逃避地の保全 | 温暖化後を見越して生物の生育域を確保する効果が期待される(Nakao et al. 2013) |
| 拡散経路の確保や拡散補助 | 生物の拡散経路となるような生態系を保全し、自律的な移動補助効果が期待される。 |
| ニホンジカによる食害影響の緩和 | 温暖化でシカが拡大する可能性が指摘されている(Ohashi et al. 2016)ため、気候変動以外の負の要因を排除することにつながる。 |
| VoCCを指標とした高山帯の野生動植物の生息域外保全 | 生態系モニタリング体制の整備や見直し、および生育域外保全に関する議論への活用が期待される(高野ほか2019; Hotta et al. 2019) |
| VoCCを指標とした適応策の検討に資する、情報共有ツールの開発 | 気候変動に伴って現在の気温と同程度の条件の場所が将来どこに移動するのか、視覚的に表示することが可能となる(高野ほか2019) |
| マツ材線虫病被害拡散前の伐採と利用 | マツ材の価値が損なわれる前に利用することで、経済的な損失を回避し、重要なマツ林等を除いて樹種転換を行うことで、対策実施地の集約化を図る(中村・大塚2019) |
| マツ材線虫病抵抗性マツの開発と利用 | マツノザイセンチュウ抵抗性品種の植栽によるマツ林の保全効果が見込まれる(中村・大塚2019) |
| 竹林の適切な管理と利用を促進し、安易な新規植栽を避ける | 竹林管理の重要性に関する啓発活動および、竹林の拡大による地域生態系サービスの質の低下防止、生物多様性維持などへの貢献が期待される(Takano et al. 2017) |
事業の成果に関する学術論文
- 髙野(竹中)宏平, 中尾勝洋, 尾関雅章, 堀田昌伸, 浜田崇, 須賀丈, 大橋春香, 平田晶子, 石郷岡康史, and 松井哲哉. 2019. “自治体の地域気候変動適応に向けたVelocity of Climate Change (VoCC)の解析.” 環境情報科学論文集 ceis33: 49-54.
- Saeko Matsuhashi, Akiko Hirata, Mitsuteru Akiba, Katsunori Nakamura, Michio Oguro, Kohei Takenaka Takano, Katsuhiro Nakao, Yasuaki Hijioka, and Tetsuya Matsui. 2020. “Developing a Point Process Model for Ecological Risk Assessment of Pine Wilt Disease at Multiple Scales.” Forest Ecology and Management 463 (March): 118010.