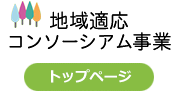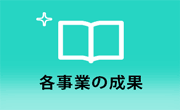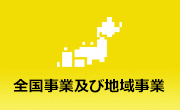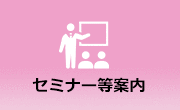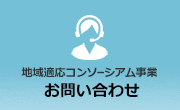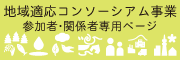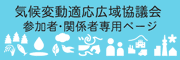海水温の上昇等によるホタテガイ及びワカメ等の内湾養殖業への影響調査に関する調査
| 対象地域 | 北海道・東北地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 先行調査 |
| 分野 | 農業・林業・水産業 |
| ダウンロード |
概要
北海道・東北地域では、ホタテガイ・ワカメ等の内湾養殖が盛んである。本調査では、青森県陸奥湾のホタテガイへの高温による影響、岩手県沿岸のワカメへの栄養塩及び、高温による影響を対象に調査を行った。ホタテガイについては、青森産技水産総合研究所が所有するへい死率予測モデルを使用した。その結果、21世紀末のRCP8.5のシナリオでは、養殖可能な海域が制限される可能性が示唆された。適応策としては、より低い水温が確保されると思われる、沖合域の水深が深い地点への、養殖施設の移動等の検討を行った。
また、ワカメについては、東北水研が所有する栄養塩予測モデルを用いて、栄養塩濃度の予測を行ったが、不確実性が大きく栄養塩の影響を検討するまでには至らなかった。一方、高温による影響について検討を行った結果、ワカメを沖に出す時期が1カ月以上遅くなることにより養殖期間が短くなり、その結果、収量が減少する可能性が示唆された。適応策としては、陸上で作成する大型種苗の利用等、短くなる養殖期間に対して、いかにして収量を維持していくか等について検討を行った。
背景・目的
ホタテガイ及びワカメは、陸奥湾やリアス式海岸等、内湾の多い北海道・東北地域において、重要な養殖対象種となっている。ホタテガイに関しては、平成22年に陸奥湾において高水温によるホタテガイの大量へい死(青森県,2011,2012)が発生しており、気候変動に伴う水温上昇によって同様の被害が発生することが予想される。
また、ワカメに関しては、近年の高水温化により海洋構造が変化し、栄養塩濃度の低下による芽落ちの被害が発生している。また、現在のところ高水温による大きな被害は出ていないものの、天然ワカメの分布南限にあたる大分県沿岸においては、冬季の高水温傾向が続いたことによるワカメの不漁が問題となっている(伊藤,2001)。以上のような状況から、今後気候変動に伴う海水温の上昇により、北海道・東北地域においても高水温による被害が発生することが予想される。そこで、①高水温がホタテガイに与える影響調査、②高水温及び栄養塩濃度の変化がワカメに与える影響調査、を目的として調査・検討を行った。また、③北海道・東北地域の関係機関が継続して連携できる枠組として内湾養殖WG(ワーキンググループ)を設置し、上記①や②の調査・検討結果を共有し、適応策に関する議論を行った。
実施体制
| 本調査の実施者 |
東北区水産研究所 資源環境部 海洋動態グループ(ワカメ) 地方独立行政法人 青森県産業技術センター水産総合研究所(ホタテガイ) 日本エヌ・ユー・エス株式会社 |
|---|---|
| アドバイザー |
東京大学 大気海洋研究所 海洋生物資源部門 環境動態分野 教授 伊藤 進一 東北区水産研究所 資源環境部 海洋動態グループ 筧 茂穂 氏 |
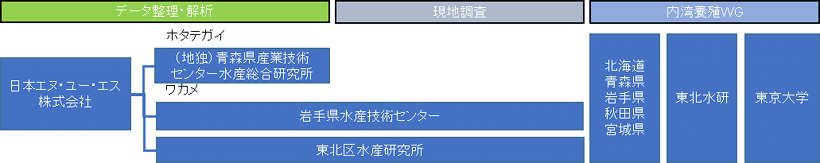
実施スケジュール(実績)
3ヶ年の実施スケジュールを図 2-2に示す。本調査では、①高水温及び栄養塩濃度の変化がホタテガイ・ワカメに与える影響に関する調査、②現地調査、③内湾養殖WGの設置、④適応策の検討、以上4点に関する取組を実施した。
平成29年度は、文献収集やヒアリングを行い、影響調査の手法に関する整理を行った。平成30年度は、提供された海洋予測データを基に、ホタテガイ・ワカメそれぞれの影響予測を行った。ホタテガイについては、青森県の陸奥湾を対象として、地方独立行政法人 青森県産業技術センター水産総合研究所(以後、青森技研水産総合研究所)が所有するホタテガイへい死率予測モデルを使用して、将来のへい死率予測を行った。また、ワカメについては岩手県沿岸を対象として、東北区水産研究所が所有する栄養塩予測モデル(Kakehi et al.,2018)を使用して、将来の栄養塩濃度の予測を行った。その他に簡易予測として、日本エヌ・ユー・エス株式会社より、北海道・東北全域におけるホタテガイ及びワカメに影響を与える高水温の出現頻度MAPを作成した。平成31年度は、平成30年度の影響予測を引き続き実施し、予測した影響を基に適応策の検討を行った。
現地調査については平成29年度に調査計画を作成し、平成30年度及び31年度の2年間にわたり調査を実施し、調査結果を栄養塩予測モデルに反映し、栄養塩がワカメ養殖に与える影響等について検討を行った。また、内湾養殖WGについては、平成29年度に2回、平成30年度及び平成31年度には年1回開催し、影響予測の手法や適応策に関して議論を行い、様々な地域の状況を共有しながら、最終的な整理を行った。
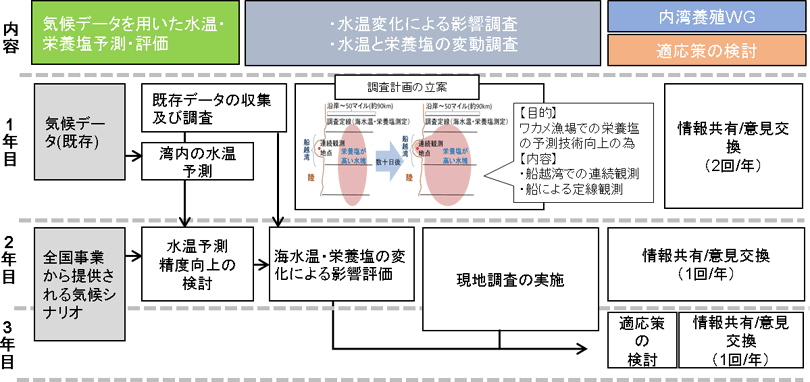
気候シナリオ基本情報
本調査で使用した気候シナリオの基本情報は、表 2-1のとおりである。
| 項目 | ホタテガイへい死率予測 ・高温出現頻度MAP |
栄養塩濃度の予測 | ワカメへの高温影響予測 | |
|---|---|---|---|---|
| 気候シナリオ名 | 海洋近未来予測力学的 ダウンスケーリングデータ by SI-CAT |
NIES統計 DSデータ |
||
| 気候モデル | MRI-CGCM3 | MRI-CGCM3 MIROC5 |
||
| 気候パラメータ | 日平均水温 | 日平均海面総熱 フラックス |
日平均気温 | |
| 排出シナリオ | RCP2.6 RCP8.5 | |||
| 予測期間 | 21世紀中頃 21世紀末 | |||
| バイアス補正の有無 | 有り(地域) | 有(全国) | ||
気候変動影響予測結果の概要
文献調査の結果、以下のことが分かった
- ホタテガイに影響を与える水温(北海道・東北広域で評価を行うために使用)。
- ワカメに影響を与える栄養塩濃度。
- ワカメに影響を与える水温。
- 地上の気温から内湾の表面水温を予測する方法。
ヒアリングでは本調査の解析手法についてご助言を頂き、影響評価の方法や気候モデルの加工の仕方に反映させながら調査を行った。また、下記の内容についてもご助言を頂いている。
- 海水温のバイアス補正方法や、必要となる観測値データについて。
- 栄養塩予測モデルに使用した、熱フラックス値の不確実性について。
影響予測を行った結果、以下のことが分かった
- 21世紀末のRCP8.5のシナリオでは、現在ホタテガイの養殖がおこなわれている水深ではへい死率が高まり、限られた海域でしか養殖できなくなる可能性が示唆された。
- 21世紀末のRCP8.5のシナリオにおいては、20℃以下となる時期が現在よりも約1カ月後ろにずれることが分かった。そのため、将来のワカメ養殖工程において芽出しの時期が遅くなる結果、養殖期間が短くなり収量が減少する可能性が示唆された。
- 高水温出現頻度MAPを作成した結果、北海道・東北全域において、ホタテガイのへい死やワカメの成長不良が発生する可能性が示唆される水温域が、今まで出現していなかった地点にまで拡大する可能性が示唆された。
ホタテガイへい死率予測
青森水総研が所有するホタテガイへい死予測モデルを使用して、陸奥湾の各水深における将来のホタテガイ稚貝及び新貝について、各々のへい死率予測を行った。各期間・シナリオ毎の結果を図 2-3、図 2-4、図 2-5に示す。現在ホタテガイの養殖がおこなわれている水深帯に最も近い水深18.5mにおける結果を見ると、21世紀末のRCP8.5のシナリオにおけるへい死率は、稚貝においては全域で80%~100%、新貝においては高水温が流入してくる西側で80%~100%、それ以外の地点においても50%~80%と、非常に高いへい死率が発生し、養殖可能な海域は沖合域等の一部に制限される可能性が示唆された。
| 水深 | 稚貝(1年貝) | 新貝(2年貝) | 凡例 |
|---|---|---|---|
| 18.5m | 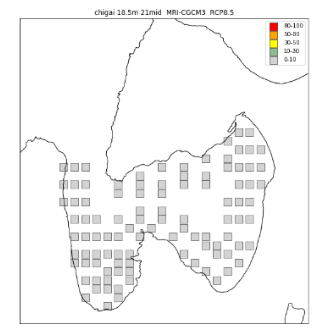 |
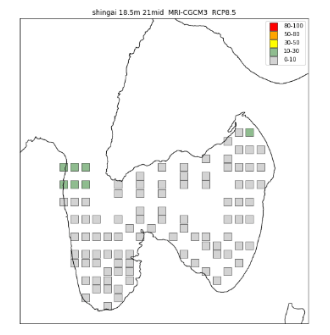 |
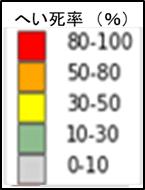 |
| 27.0m | 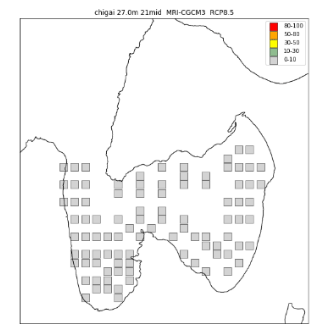 |
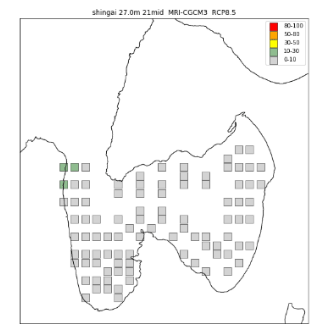 |
|
| 38.0m | 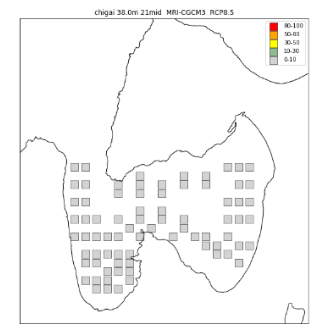 |
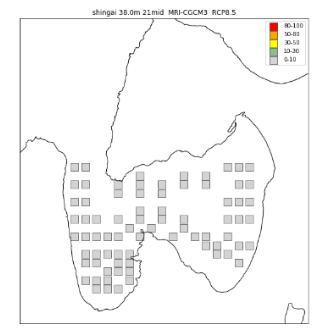 |
|
| 51.0m | 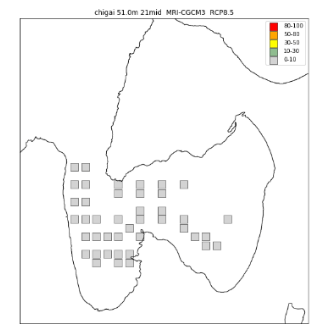 |
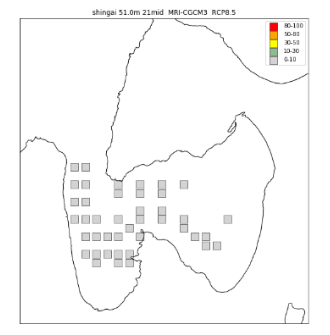 |
(21世紀中頃 MRI-CGCM3 RCP8.5)
| 水深 | 稚貝(1年貝) | 新貝(2年貝) | 凡例 |
|---|---|---|---|
| 18.5m | 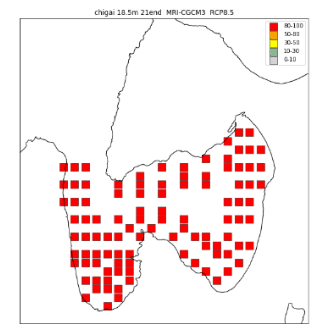 |
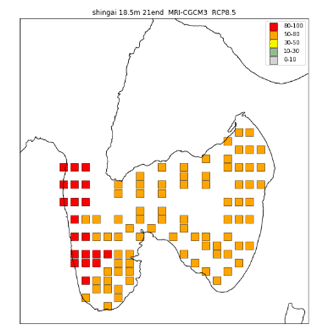 |
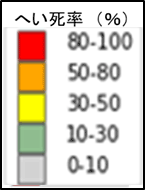 |
| 27.0m | 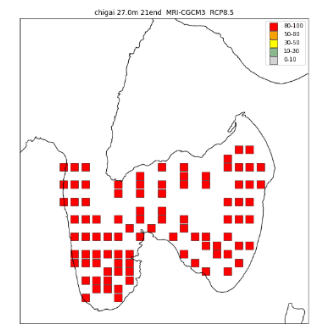 |
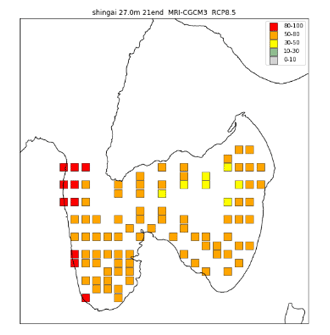 |
|
| 38.0m | 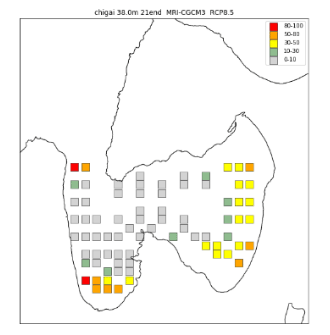 |
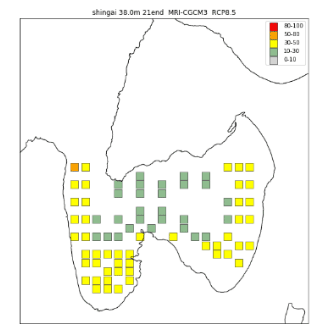 |
|
| 51.0m | 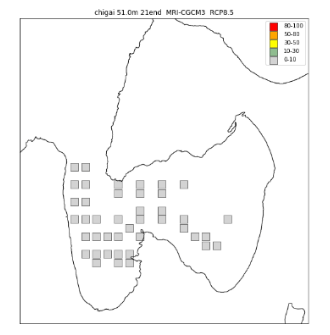 |
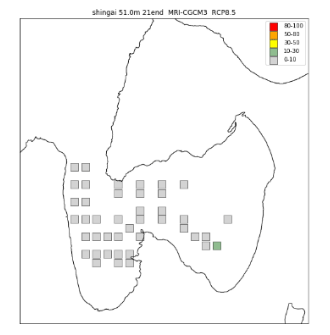 |
(21世紀末 MRI-CGCM3 RCP8.5)
| 水深 | 稚貝(1年貝) | 新貝(2年貝) | 凡例 |
|---|---|---|---|
| 18.5m | 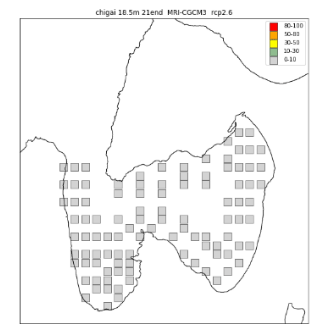 |
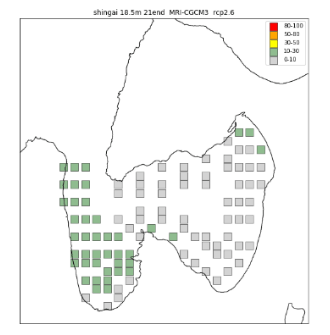 |
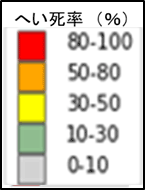 |
| 27.0m | 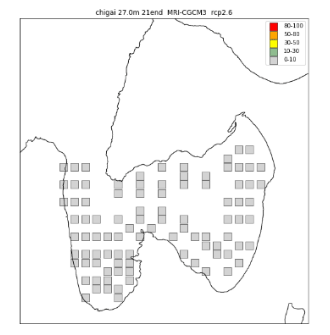 |
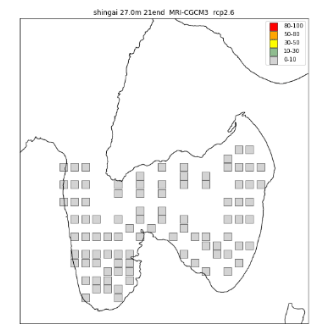 |
|
| 38.0m | 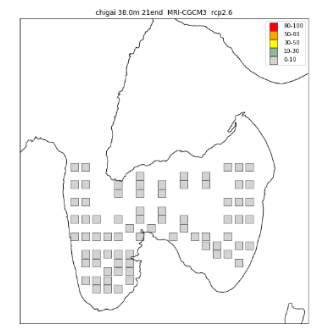 |
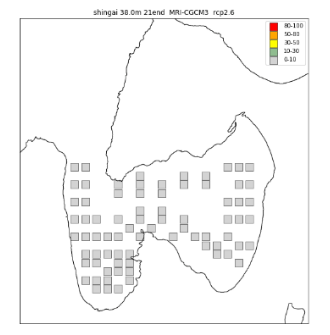 |
|
| 51.0m | 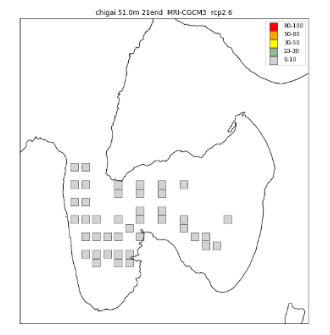 |
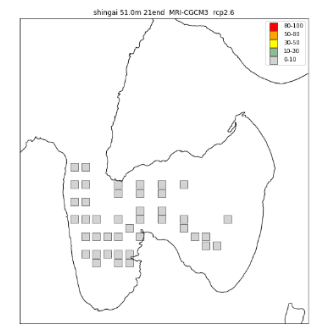 |
(21世紀末 MRI-CGCM3 RCP2.6)
ワカメへの高温影響予測
ワカメは、20℃以下となると配偶体の成熟を開始し、養殖工程では20℃以下を目安としてワカメの芽出しを行っている(岩手県,2007)。そこで、秋季の高温により、船越湾の水温が20℃以下となる時期が、いつ頃になるのかについて予測を行った。気温の予測データを使用して、船越湾において水温が20℃以下となる時期を求めた。結果を図 2-6、図 2-7、図 2-8、図 2-9に示す。
予測の結果、現在では10月3日頃に20℃以下となるのに対して、MRICC5及びMRI-CGCM3の気候モデルでは21世紀中頃で10日程度、21世紀末RCP8.5のシナリオでは1カ月以上後ろにずれ、芽出しの時期が遅くなることが予測された。芽出しの時期が遅くなることで、図 2-10に示す養殖管理の期間は短くなるため、ワカメの収量が減少する可能性があることが分かった。
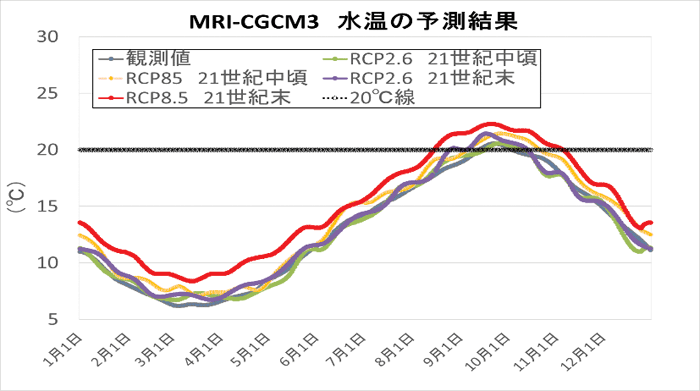
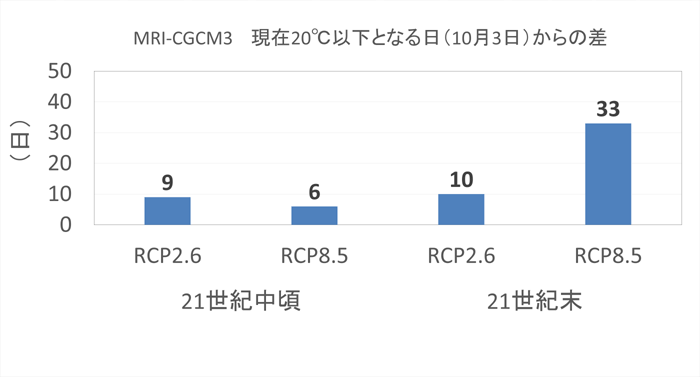
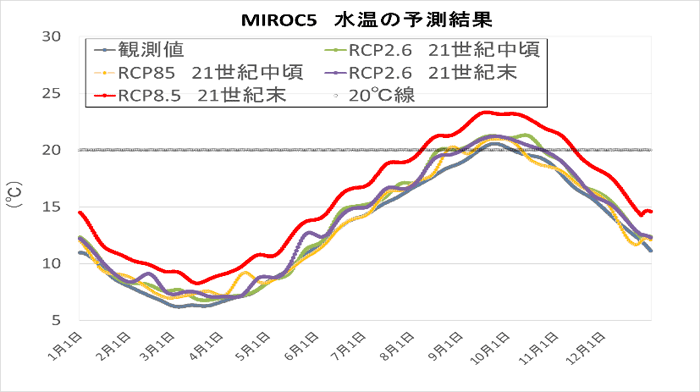
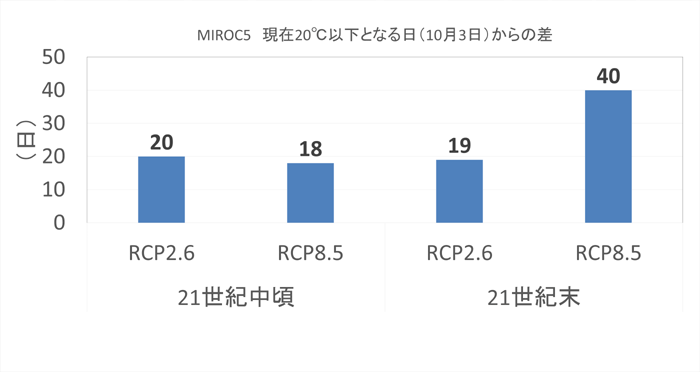
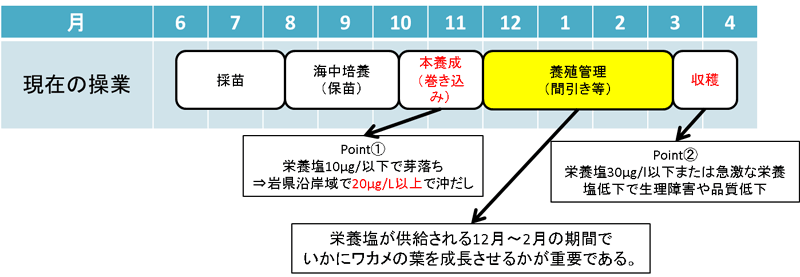
高水温出現頻度MAP
文献調査の結果から得られた、ホタテガイ養殖に影響を与える水温の情報を基に、高水温の出現頻度MAPを作成し、北海道・東北地域における簡易予測を実施した。
【ホタテガイ】
21世紀末のRCP8.5の結果では、ホタテガイの養殖が行われている噴火湾や三陸沿岸においても、25℃以上の高水温が発生し、へい死の危険性が高まることが分かった(表 2-2)。なお、現在の気温及び21世紀中頃に予想される気温では、当該海域において25℃以上の高水温は確認されていない。
【ワカメ】
21世紀中頃及び21世紀末におけるRCP8.5の結果では、ワカメの養殖が行われている三陸沿岸において、現在の気候では確認されていない15℃以上の高水温が予想され、高水温による葉の成長不良が発生する可能性が高まることが分かった(表 2-3)。
(MRI-CGCM3)
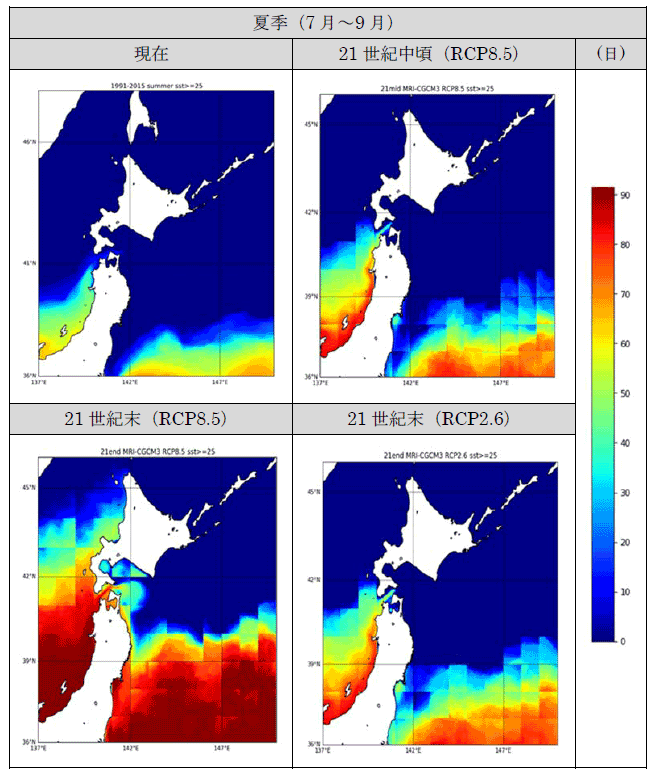
(MRI-CGCM3)
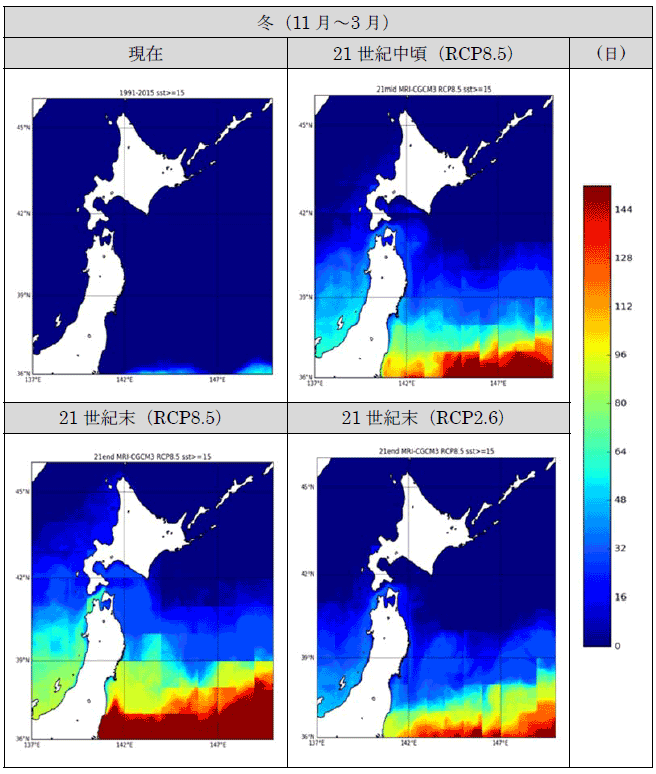
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
【ホタテガイへい死率予測】
使用した水温データは、水深毎にバイアス補正を行っている。なお、観測値がない水深帯については、内挿による補正を行っている点に注意が必要である。
【高水温出現頻度MAP】
バイアス補正の都合上、表面水温のみの影響評価となっている。養殖施設は、表面より少し深い地点に設置されていることが多いが、水深が深いほど水温は低くなるため、予測値が若干過大評価となっていることが予想される。
【ワカメへの高温影響予測】
内湾の1地点における予測結果である。内湾は湾の向きと海流の流れにより、水温が大きく変化することがある。その点について考慮していない点に注意が必要である。
本調査の将来予測の対象外とした事項
【ホタテガイへい死率予測】
ホタテガイのへい死には、水温の他、下記の要素も影響すると考えられる。ただし、本調査において気候変動影響予測を実施するに当たり、下記の影響を考慮していないことについて留意が必要である。
- 貧酸素による影響
- 餌環境の変化による影響
- 波高や流速による影響
【ワカメへの高温影響予測】
ワカメに対する気候変動の影響については、水温及び栄養塩の他、下記の要素も影響すると考えられる。ただし、本調査において気候変動影響予測を実施するに当たり、下記の影響を考慮していないことについて留意が必要である。
- 照度・光量による影響
- 塩分による影響
- 栄養塩濃度の影響
その他、成果を活用する上での制限事項
【ホタテガイへい死率予測】
- 陸奥湾のホタテガイや水温の観測情報を基に作成されたモデルであるため、状況の異なる他の養殖地域に適用することは難しい。
適応オプション
調査において検討した適応オプション及びその考え方を表 2-4~表 2-7に示す。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 養殖施設の移動 | ● | ● | 普及している |
|
△ | △ | △ | ◎ | 短期 | 高 | |
| 代替種の導入 | ● | ● | - |
|
◎ | △ | △ | △ | 長期 | 低 | |
| 陸上養殖の実施 | ● | ● | - |
|
△ | △ | △ | △ | 長期 | 低 | |
| 高温耐性品種の導入 | ● | ● | - |
|
△ | △ | △ | △ | 長期 | 低 | |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| 養殖施設の移動 | 過去に発生した高水温によるへい死被害の際にも、養殖施設を深く沈める対策が実施され効果も確認されている。(青森水総研、青森県庁へのヒアリング結果より) |
| 代替種の導入 | 平成22年に高水温によるホタテガイの大量へい死が発生した際に、別の養殖種としてアカガイやホヤについての検討が行われている。代替種の導入に向けた必要経費についての支援や、適当な代替種の検討及び導入試験等については行政が行い、現場での実施は漁業者が行っていく体制になると思われる。(青森水総研、青森県庁へのヒアリング、内湾養殖WGのヒアリング結果より) |
| 陸上養殖の実施 | 現時点で、導入に必要な知見が十分ではないため、情報面を-としている。新たに情報を収集し、陸上養殖を実施するための試験を実施し、知見や経験を蓄積するためには、多くの時間やコストが必要になると想定される。 |
| 高温耐性品種の導入 | 現時点で、導入に必要な知見が十分ではないため、情報面を-としている。高温下での養殖が可能な品種を作出できたとしても、需要に十分に対応できるだけの高温耐性の種苗を安定的に供給するためには、さらに種苗生産技術の開発が必要になることから、高温耐性品種の導入までには非常に長い時間と、多額の研究費や新たな研究施設や種苗生産施設が必要になると思われるため、物的面及びコストに関しては△としている。 |
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 大型人工種苗の導入 | ● | ● | 普及している |
|
△ | △ | △ | ◎ | 短期 | 高 | |
| 栄養塩予測モデルの活用 | ● | ● | 普及している |
|
◎ | △ | △ | △ | 長期 | 高 | |
| 高温耐性品種及びワカメの南方種の導入 | ● | ● | - |
|
◎ | △ | △ | - | 長期 | 低 | |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| 大型人工種苗の導入 | 現在研究が進められており、既に現場への導入実績及び効果が得られている方法である。実施主体としては、陸上施設での種苗生産に関する、労力及びコストに対する支援は行政が担うのが適切であると考えるが、実施の可否については漁業者が周囲の状況を勘案しながら判断する必要がある。(岩手県水産技術センターヒアリング、大型人工種苗導入例 (岩手県水産技術センターHP参照:http://www2.suigi.pref.iwate.jp/info/20171128news) |
| 栄養塩予測モデルの活用 | 現在、既にワカメ養殖の現場で導入されており、秋季の栄養塩の供給時期については、かなりの精度で予測が可能となっている。ただし、春季の栄養塩の枯渇については、さらなる精度の向上が課題となっている。(東北区水産研究所、岩手県水産技術センターヒアリング、栄養塩予測モデル導入例 (岩手県水産技術センターHP参照:http://www2.suigi.pref.iwate.jp/research/20191028undaria_farming) |
| 高温耐性品種及びワカメの南方種の導入 | 高温耐性の種苗を導入するための知見が十分ではない。地場産の高温耐性品種の選抜育種には時間を要することと異なる地域のワカメを利用するため、これまで築いてきた三陸ワカメのブランド、具体的には葉の厚さや歯ごたえあるワカメを存続させることは難しいと考えられる。その意味において、本適応オプションは三陸ワカメを対象とした適応策とはならないため、効果の程度を低いと考えられる。 (岩手県水産技術センターヒアリング、内湾養殖WGヒアリング結果) |