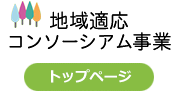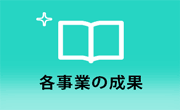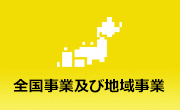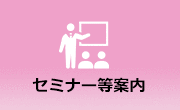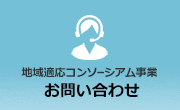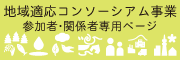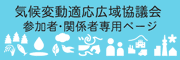海水温の上昇等によるシロザケ等の漁獲量への影響に関する調査
| 対象地域 | 北海道・東北地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 先行調査 |
| 分野 | 農業・林業・水産業 |
| ダウンロード |
概要
シロザケ(サケ)は、北海道・東北地域の重要な水産資源となっており、ふ化放流事業は資源の維持・増大のために大きな役割を担っている。近年、サケの回帰率減少が問題となっており、湾内の高水温による放流稚魚の減耗が一因と言われている。放流後、湾内を遊泳する幼稚魚は、13℃以上となると北上するといわれており、それまでに生理学的、解剖学的に十分な成長を終え、北上回遊による環境変化に耐えうるだけの体力を蓄えておく必要がある。
宮城県では最適な回帰率を得るために、①稚魚を5㎝以上で放流すること、②13℃以上になる前に、幼稚魚が湾内で12㎝以上に成長するために必要な期間を逆算して放流すること、の2点を考慮して放流適期が設定されている。本調査では、北上を開始する水温である13℃を指標に、将来の宮城県沿岸域の水温を予測し、放流適期がどのように変化するかについて検討を行った。その結果、21世紀中頃と21世紀末におけるRCP2.6の気候シナリオでは、現在より放流適期が短縮し、特に21世紀末のRCP8.5気候シナリオにおいては、宮城県沿岸は常に13℃以上となり、放流適期が消滅する可能性が示唆された。これらの結果が得られたことから、将来予想される高水温環境においても、ふ化放流事業を継続するために必要となる適応策について検討を行った。
背景・目的
シロザケ(サケ)は、北海道・東北地域の重要な水産資源であり、ふ化放流事業は資源の維持・増大のために大きな役割を担っている。近年、サケの回帰率減少が問題となっており、その要因の一つとして放流時の沿岸水温による影響(宮腰, 2007やSaito, 2002)が報告されている。今後、気候変動に伴う沿岸域の水温上昇により、サケ放流種苗の生産から放流するまでの工程に影響が生じ、適切な放流稚魚のサイズや放流時期を維持できなくなる可能性が考えられる。その結果、回帰率の低下を招くこととなり、漁獲量に悪影響が生じることが懸念される。
本調査では、サケの放流適期に関する情報の整理や、サケ放流時の水温がサケの回帰率に与える影響等について調査を行い、宮城県において将来の高海水温環境においても実施可能な、ふ化放流事業に必要となる適応策の検討を目的に調査・分析を行った。
実施体制
| 本調査の実施者 | 日本エヌ・ユー・エス株式会社 |
|---|---|
| アドバイザー | 北海道大学 大学院水産科学研究院 海洋生物資源科学部門 教授 工藤 秀明 |
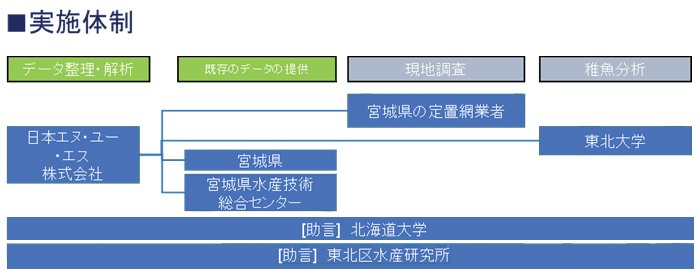
実施スケジュール(実績)
3ヶ年の実施スケジュールを図 3-2に示す。本調査の内容は、以下の3項目に大別される。第一に、サケと回帰率に関する既存知見の収集・整理を行い、調査計画策定・影響評価・適応策検討に必要となる、基本的な知見を取り纏めた。第二に、将来の水温データから予想される放流適期を求め、高水温の影響について評価分析を行った。第三に、サケの将来の高海水温環境に合わせたふ化放流事業を実施するために必要となる適応策について、影響評価や現地調査の結果に基づき検討を行った。
平成29年度の調査では、サケの影響評価モデル構築に向けて既存データの収集・整理、及び水温観測とサケ幼稚魚の採捕・分析計画の立案を実施した。
平成30年度の調査では、本事業で提供される海洋近未来予測力学的ダウンスケーリングデータ(将来予測データ)を用いて、平成29年度に整理した内容、及び新たに文献調査やヒアリングにより収集した情報を参考にして、宮城県の放流適期の将来予測、及び海水温がサケの回帰率に与える影響に関する情報の整理を行った。また、宮城県の沿岸域においてサケ幼稚魚のサンプリング調査を実施した。得られたサンプルについて、耳石、骨格、胃内容物等について分析を行い、降海後のサケ幼稚魚が滞留する、沿岸域の生活環境に関する調査を行なった。平成31年度には、影響評価モデルの精度向上のため、有識者へのヒアリングを実施した他、さらなる文献調査を実施して最新の知見を整理し、調査対象地域における海水温等が、サケに与える影響について評価検討を行った。また、得られた影響評価の結果に基づき、適応策の検討を行った。
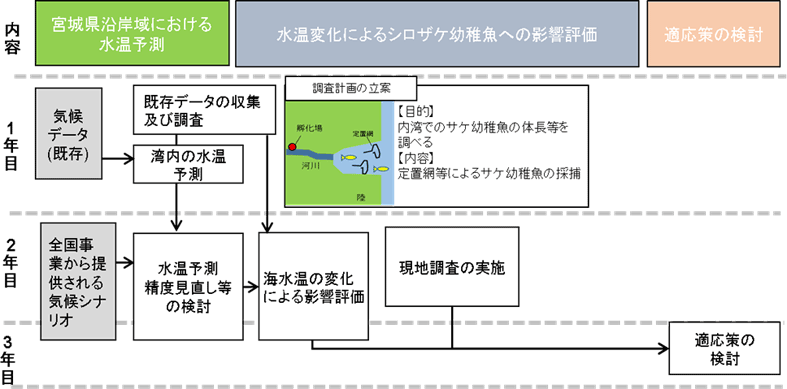
気候シナリオ基本情報
本調査で使用した気候シナリオの基本情報は、表 3-1のとおりである。
| 項目 | シロザケの放流適期予測 |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | 海洋近未来予測力学的ダウンスケーリングデータ by SI-CAT |
| 気候モデル | MRI-CGCM3 |
| 気候パラメータ | 海面水温 |
| 排出シナリオ | RCP2.6 RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀中頃 21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 有り(地域) |
気候変動影響予測結果の概要
文献調査の結果、以下のことが分かった。
- サケの回帰率と、放流後のサケ幼稚魚が滞留する沿岸域の水温との相関は高く、高水温が回帰率に影響する可能性があることが分かった。
- 放流後の幼稚魚が沿岸域で滞留している時期の生活史が分かった。
ヒアリングで調査の結果、以下のことが分かった。
- 現地調査で採捕したシロザケ稚魚の分析結果から、尾叉長10cm程度のサイズが多く、また、降海後の日輪数と筋肉の安定同位体分析の結果から、1ヶ月以上にわたって海洋生活を送っていることが分かった。
- 採捕したシロザケ幼稚魚の骨格形成は、既に骨化4) が終了していることが確認された。
- 適応策を検討する上で、地域毎に課題や状況が異なることが分かった。
影響予測を行った結果、以下のことが分かった。
- Saito(2002)を参考としながら、海水温が回帰率に与える影響について解析を行ったが、宮城県における放流後の水温と、回帰率との関係を明らかにすることができなかった。(検討結果の詳細については、エラー! 参照元が見つかりません。に示す)
- 放流適期について将来予測を行った結果、21世紀中頃や21世紀末のRCP2.6のシナリオにおいては、現在よりも放流適期が短縮することが示唆された。
- 放流適期の将来予測を行った結果、21世紀末のRCP8.5のシナリオにおいては、放流適期が消滅する可能性のあることが示唆された。
シロザケの放流適期予測
本調査では、現在宮城県において放流適期の基本情報として利用されている、昭和50年代に作成された放流適期図(以下、「宮城県放流適期図(昭和版)」という)について、まずは現在の水温に対応させて、放流適期図(北部・南部)の再構築を行った。さらに、再構築した放流適期図に将来の水温を与えて、宮城県の放流適期を予測した。結果を図 3-3、図 3-4、表 3-2に示す。各図の赤い太線箇所が、放流適期期間を示している。宮城県北部・南部両地点において、21世紀中頃と21世紀末におけるRCP8.5のシナリオでは、放流適期が縮小することが分かった。また、シナリオRCP8.5の21世紀末のケースでは、宮城県沿岸域において13℃以上の水温が継続してみられ、放流適期が消滅する可能性のあることが分かった。
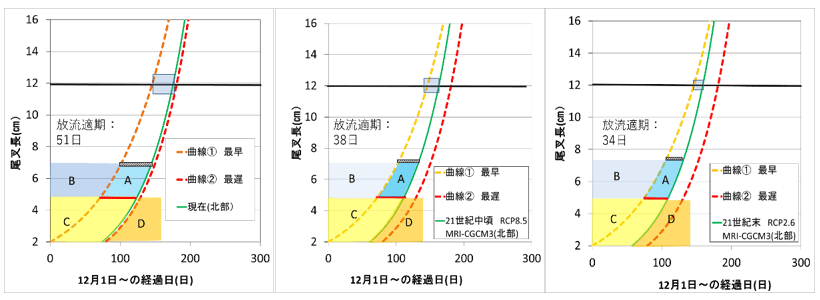
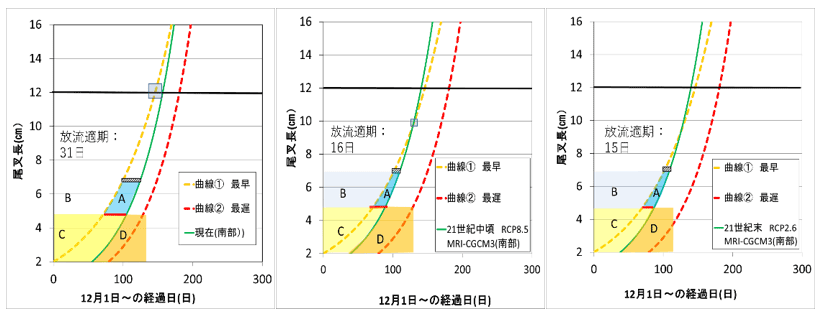
| 北部 | |||
|---|---|---|---|
| 13℃に達する日数 | 5cmに達する日数 | 放流適期期間 | |
| 現在 北部 (観測値データを基に作成) |
177日 (5月27日) |
126日 (4月6日) |
51日 |
| 21世紀中頃 北部 MRI-CGCM3 RCP8.5 |
164日 (5月14日) |
113日 3月24日 |
38日 |
| 21世紀末 北部 MRI-CGCM3 RCP2.6 |
160日 (5月10日) |
109日 (3月20日) |
34日 |
| 21世紀末 北部 MRI-CGCM3 RCP8.5 |
常に13℃以上 | ||
| 南部 | |||
|---|---|---|---|
| 13℃に達する日数 | 5cmに達する日数 | 放流適期期間 | |
| 現在 南部 (観測値データを基に作成) |
158日 (5月8日) |
107日 (3月18日) |
31日 |
| 21世紀中頃 南部 MRI-CGCM3 RCP8.5 |
142日 (4月22日) |
91日 (3月2日) |
16日 |
| 21世紀中頃 南部 MRI-CGCM3 RCP2.6 |
141日 (4月21日) |
90日 (3月1日) |
15日 |
| 21世紀末 南部 MRI-CGCM3 RCP8.5 |
常に13℃以上 | ||
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
本調査では下記2点に留意する必要がある。
- 降海後の幼稚魚が沿岸域において滞留している時期から、沖合域を北上するまでの時期を影響評価の対象としている。
- 上記の評価対象以外の期間となる、親魚の回帰時期あるいは種苗飼育時等の環境条件は、現在と変わらないと仮定している。
本調査の将来予測の対象外とした事項
本調査において、下記の影響は考慮していないことに留意が必要である。
- 降海後に幼稚魚が滞留する沿岸域での急激な水温変化
- 親魚回帰時の水温
- 種苗生産用の卵の確保(親が回帰して、種苗生産用の卵が確保できることを前提)
- 放流幼稚魚の健苗性
その他、成果を活用する上での制限事項
本調査は、宮城県で実際使用されている放流適期図を基に予測を行っている。放流適期は各地域の環境条件等に左右されるため、他の地域に同じ手法を適用することは難しい。
適応オプション
調査において検討した適応オプション及びその考え方を表 3-4~表 3-5に示す。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 沖合移動期の尾叉長引き下げによる放流適期の見直し5) | ● | ● | - | 適切な尾叉長設定のため、更なる調査、分析が必要 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | 短期 | 高 | |
| 放流適サイズに達するまでに必要な種苗飼育期間の短縮(加温飼育等) | ● | ● | - | 新たなコスト負担を考えると、現状では設備の増設や、労働力の確保が難しい。 | △ | △ | △ | ◎ | 短期 | 中 | |
| 飼料や飼育環境改善による幼稚魚の健苗性向上 | ● | ● | - | 新たなコスト負担を考えると十分な予算確保が難しい。 | △ | △ | △ | ◎ | 短期 | 中 | |
| 高温耐性品種の活用 | ● | ● | - | 県内の種苗だけで、21世紀末に予想されている水温に耐えられる品種を作出できるか不明である。 遺伝的劣化が影響として懸念される。 |
△ | △ | △ | △ | 長期 | 低 | |
- 行政は県庁と水産試験場を想定している
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 沿岸漁獲のサケの利用 (海産卵) |
● | ● | 一部普及されている | 早期の種苗卵確保が目的であるが、サケの回帰率が大きく減少しないことが前提になる。 | △ | △ | △ | ◎ | 長期 | 低 | |
| 野生魚の活用6) | ● | ● | - | 環境収容力を超える数のサケが遡上した場合、あるいはサケが遡上していない河川にサケが遡上した場合には、遡上河川の生態系に悪影響が及ぶ可能性がある。 | △ | △ | △ | ◎ | 長期 | 中 | |
| 代替種の検討 | ● | - | サケと同程度の規模を代替できる水産種を考えるのは難しい。 漁業者や加工業者等、水産業界全体を考慮する必要がある。 |
△ | △ | △ | - | 長期 | 低 | ||
- 行政は県庁と水産試験場を想定している
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| 沖合移動期の尾叉長引き下げによる放流適期の見直し |
回帰率が良いといわれるサケの放流には、下記の3つの条件がある。
沖合移動を12cmと設定している宮城県では、一般的な設定である7㎝よりも、長く沿岸域で成長させる必要があるため、早く放流している。本事業にて現地調査を行ったところ10㎝でも沖合移動に十分な大きさであることが分かったため、沖合移動の設定を12cmから10cm以下に変更することで、 |
| 放流適サイズに達するまでに必要な種苗飼育期間の短縮(加温飼育等) |
放流種苗が、放流適サイズに達するまでに必要な飼育期間を短縮する方法としては、下記に示す2つの方法が想定される。
両方法とも、現在研究が行われている分野である。①②のどちらの方法を採用するにしても、新たな労力や設備等が必要となる。回帰率への影響については、現在も盛んに研究されている分野であるが、様々な原因が想定される非常に難しい課題となっており、未だ不確実な部分が多いため、期待される程度は中としている。(北海道大学工藤先生、宮城県庁、宮城県水産研究センターヒアリングより) |
| 飼料や飼育環境改善による幼稚魚の健苗性向上 | 高カロリーの餌を与えることにより、早く大きく育てるだけでなく、体力的に温度耐性がある優良種苗を生産する適応オプションである。ある程度の温度耐性及び生存率向上は期待できるが、温暖化で予想される高水温に対しての適応可否については不明な点が多い。(北海道大学工藤先生ヒアリングより) |
| 高温耐性品種の活用 | 今年度のサケ回帰率の低下を受けて、岩手県が研究に着手した段階であり、今後知見は増えていくことが予想される。宮城県内で適応オプションとして検討する場合には、県内の種苗を利用した品種改良(生物多様性を考慮)を想定している。 |
| 沿岸漁獲のサケの利用(海産卵) | 岩手県等で実際に導入されている手法である。(参照:2019年12月16日水産経済新聞「放流用卵、市場で調達」)河川遡上する前のサケを沖捕りし、できるだけ早い時期に、種苗生産のための卵を確保する方法であり、適応オプションの「放流適サイズに達するまでに必要な種苗飼育期間の短縮」②の方法に関係する内容となる。沖で捕獲したサケの場合には、採卵に高度な技術が必要となる。(宮城県庁、宮城県水産総合研究センターヒアリングより) |
| 野生魚の活用 | 野生魚活用については、シミュレーション(大熊ら,2016)や現地調査等(森田ら,2013)による研究が行われており、非常に注目されているテーマである。しかし、関連情報の多くは北海道の大きな河川での事例であるため、宮城県の河川でも同様の効果が期待できるかについては検討が必要である |
| 代替種の検討 | サケは北日本において、古くから多種多様な利用がされており、地元では最も重要な水産物である。したがって、サケと同様の価値が期待できる代替種を探すことは非常に困難であると思われる。サケを扱っている漁業者、加工業者、流通業者等、影響する幅広い範囲を考慮すると、期待される効果の程度は低いと考えられる。 |