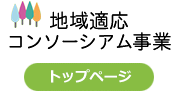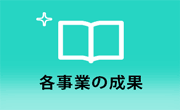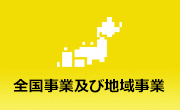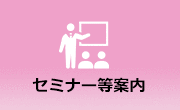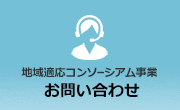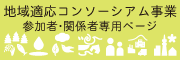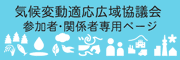気温上昇や降水量の変化等による釧路湿原の水環境・生態系への影響に関する調査
| 対象地域 | 北海道・東北地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 率先調査 |
| 分野 | 水環境・水資源 自然生態系 |
| ダウンロード |
概要
釧路湿原は、北海道東部を流れる釧路川に沿って広がる、日本最大の湿原である。釧路湿原は、生物多様性の観点からだけでなく、Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)や地域産業(観光業)の観点からも重要であり、将来にわたり保全していくことが求められている。しかし、近年、大雨時の出水に伴い釧路湿原に多量の土砂・栄養塩が流入することで、湿原植生が急速に変化していることが保全上の課題となっている。また、将来の気候変動により、大雨の頻度・強度が増大すると、釧路湿原の水環境や生態系にもさらに大きな影響が及ぶと推測される。本調査では、釧路湿原における大雨の頻度・強度の増大及びそれに伴う影響(土砂・栄養塩負荷量の変化及びEco-DRR機能)を予測し、それらに対する適応策を検討した。
その結果、21世紀末(RCP8.5シナリオ)においては、釧路川やその支川の大雨時の流量が最大約2倍に増大することが予測された。また、それに伴い、土砂・栄養塩負荷量も大幅に増大すること、釧路湿原の保水機能の重要性がさらに増すことが予測された。こうした影響に対する適応策としては、河道の安定化や河川沿いの未利用農地の活用による土砂・栄養塩流入対策などが想定された。
背景・目的
釧路湿原は、北海道東部を流れる釧路川に沿って広がる、日本最大(面積:約258平方キロメートル)の湿原である。その原生的な自然は、生物多様性の観点からだけでなく、Eco-DRR(生態系を活用した防災・減災)や地域産業(観光業)の観点からも重要であり、将来にわたり保全していくことが求められている。その一方で、北海道東部においても、将来、気温の上昇や降水量の増大といった気候変動が予想されている。これにより、釧路湿原の水環境や生態系にも様々な影響が及ぶと推測される。
本調査の目的は、こうした気候変動に伴う釧路湿原の水環境や生態系への影響を評価し、その結果に基づき釧路湿原の保全に資する適応策を検討することである。本調査では、特に、将来想定される大雨の頻度・強度の増大に伴う影響に着目した。その理由は、大雨時の出水が、①湿原への大量の土砂・栄養塩流入を引き起こし、釧路湿原の保全上既に大きな問題となっていること、また、②釧路川下流部に位置する釧路市や釧路町の防災上も重要であること、の2点である。大雨の頻度・強度の増大に伴う釧路湿原の水環境(湿原内を流れる河川の流量や土砂・栄養塩負荷量)の変化を、可能な限り定量的に評価した。また、その結果に基づき、釧路湿原の生物多様性やEco-DRR機能を維持・向上させるための適応策の検討を目的に調査・検討を行った。
実施体制
| 本調査の実施者 | 北海道、日本エヌ・ユー・エス株式会社 |
|---|---|
| アドバイザー | 北海道大学 教授 中村 太士 |
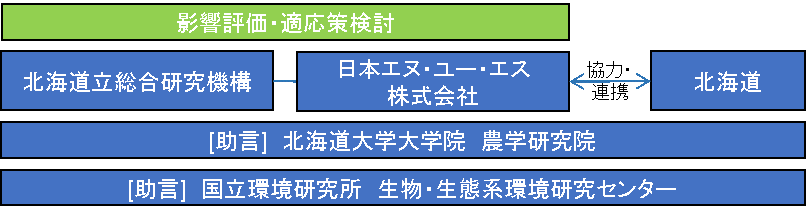
実施スケジュール(実績)
2ヶ年の実施スケジュールを図 6-2に示す。本調査の内容は、次の3項目に大別される。第一に、釧路湿原に関する既存知見の収集・整理を行い、調査計画策定・影響評価・適応策検討の参考とした。第二に、大雨の頻度・強度の増大に伴う釧路湿原への影響評価を実施した。具体的には、まず、気候シナリオデータを用いて、将来の大雨の頻度・強度を評価した。次に、将来の大雨を想定した釧路湿原の水循環シミュレーションを実施し、釧路湿原の持つEco-DRR機能を評価した。最後に、湿原内を流れる各河川の流量変化と、各河川のL-Q式(河川のある地点における、流量Qと流出負荷量Lとの関係式)から、各河川の土砂・栄養塩流入量の変化を評価した。第三に、釧路湿原の生物多様性やEco-DRR機能を維持・向上させる適応策を、影響評価や現地調査の結果に基づき検討した。
平成30年度の調査では、①釧路湿原に関する既存知見の収集・整理、②気候シナリオデータを用いた将来の大雨の頻度・強度評価、③釧路湿原のEco-DRR機能評価に向けた水循環シミュレーション、④適応策検討に向けた現地調査の準備、の4点を実施した。
平成31年度の調査では、①大雨の頻度・強度評価手法の見直し、②将来の大雨の頻度・強度のより精緻な評価結果を用いた水循環シミュレーション、③L-Q式を用いた土砂・栄養塩流入量の変化評価、④適応策検討に向けた現地調査、⑤適応策の検討、の5点を実施した。
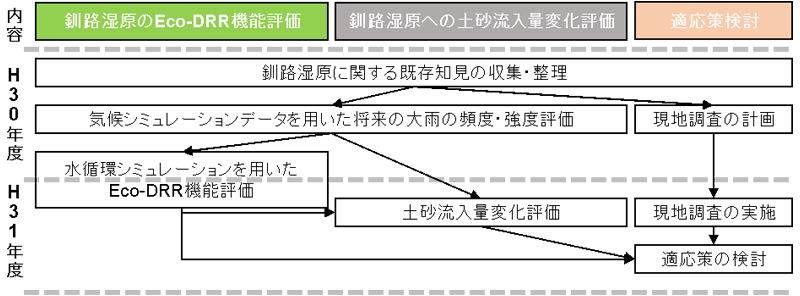
気候シナリオ基本情報
本調査で使用した気候シナリオの基本情報は、表 6-1のとおりである。
| 項目 | Eco-DRR機能の評価、土砂・栄養塩流入量変化 |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | 気象研究所2km力学的DSデータ by 創生プログラム |
| 気候モデル | MRI-NHRCM02 |
| 気候パラメータ | 降水量 |
| 排出シナリオ | RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 有り (全国) |
気候変動影響予測結果の概要
文献調査では、以下のことが分かった。
- ①釧路湿原の保全上の課題として、現在特に注目されているのは、大雨時の出水に伴う多量の土砂・栄養塩流入である。これにより、ハンノキ林が増加するなど、湿原植生が急速に変化している(釧路湿原自然再生協議会, 2015)。
- ②現在、釧路湿原への土砂流入対策として、河道の安定化などの発生源対策、河畔林などの緩衝帯整備、土砂調整地などによる出水時土砂捕捉、といった施策が実施されている(釧路湿原自然再生協議会, 2019)。
ヒアリングでは、以下のことが分かった。
- ①釧路湿原が持つ多様な価値を示すことが、普及啓発、ひいては釧路湿原の保全に繋がることから、釧路湿原の保水機能を評価項目に加えるべきことが分かった。また、釧路湿原自然再生事業において構築された水循環モデルがあり、現況再現性も確認されていることから、本調査の影響予測において採用すべきことが分かった(北海道大学 中村教授)。
- ②釧路湿原では、釧路湿原自然再生協議会による再生・保全事業が進められており、それらのうちのいくつかは、そのまま適応策としても有効であることが分かった(釧路自然環境事務所、釧路開発建設部)。
影響予測を行った結果、以下の2つの結果が得られた。
- ①釧路湿原の保水機能により、釧路湿原で大規模な出水が発生した2016年8月の大雨時、釧路川下流部ではピーク流量が約160 m3/s低下し、ピークの到達が2日間遅延した、と評価された。また、21世紀末(RCP8.5シナリオ)の大雨時の予測計算では、ピーク流量の低下は約360 m3/sと評価され、釧路湿原の保水機能の重要性がさらに増すことが示唆された。
- ②釧路湿原に流入する3河川(久著呂川、雪裡川、幌呂川)におけるSS(浮遊土砂)・全窒素・全リン負荷量は、大雨時の流量の増大(1.7~2.2倍)に伴い、大幅に増大(SS:4.3~8.3倍、全窒素:2.3~3.3倍、全リン:2.6~4.2倍)することが示唆された。
Eco-DRR機能の評価
釧路湿原の保水機能を評価するために、釧路湿原自然再生事業において構築された水循環モデルを用いて、現在及び21世紀末(RCP8.5シナリオ)の大雨時における釧路川下流部(広里)でのピーク流量を、湿原がある場合とない場合とで比較した。現在の降水量としては、釧路湿原で大規模な出水が発生した2016年の観測日降水量を用いた。また、21世紀末の降水量は、2016年の観測日降水量に、現在から21世紀末への日降水量の変化率を乗じることで推計した。
その結果、2016年8月の大雨時の再現計算では、釧路湿原の保水機能により、ピーク流量が約160 m3/s低下し、ピークの到達が2日間遅延した、と評価された(図 6-3)。また、21世紀末(RCP8.5シナリオ)の大雨時の予測計算では、ピーク流量の低下は約360 m3/sと評価され、現在よりもその重要性が増すことが示唆された(図 6-4)。
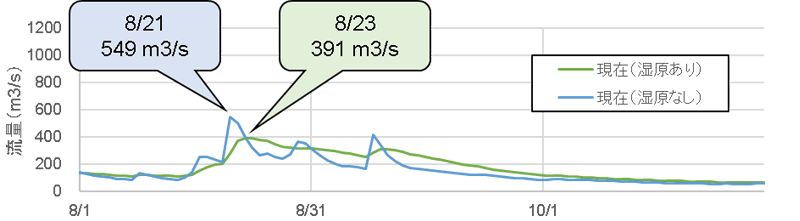
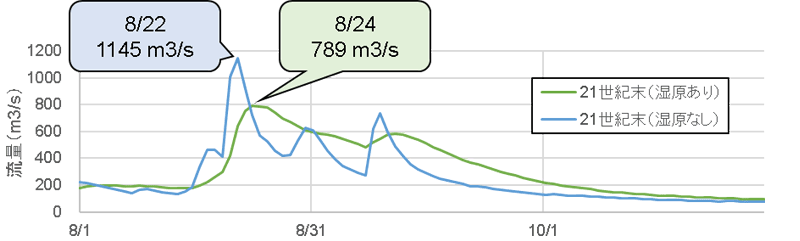
土砂・栄養塩流入量変化
釧路湿原に流入する3河川(久著呂川、雪裡川、幌呂川)を対象として、現在及び21世紀末(RCP8.5シナリオ)における土砂・栄養塩負荷量を推計した。各河川の現在及び21世紀末の流量は、Eco-DRR機能評価と同様に、水循環シミュレーションにより求めた。さらに、釧路湿原自然再生事業で得られたL-Q式を用いて、浮遊土砂(SS)・全窒素・全リン負荷量の変化を評価した。
その結果、21世紀末(RCP8.5シナリオ)では各河川の大雨時のピーク流量は1.7~2.2倍に増大すると予測された。また、流量の増大に伴い、SS(浮遊土砂)・全窒素・全リン負荷量も大幅に増大することが示唆された(表 6-2、表 6-3、表 6-4)。
| 久著呂川 | SS(kt/年) | 全窒素(t/年) | 全リン(t/年) |
|---|---|---|---|
| 現在 | 62.4 | 368 | 45.3 |
| 21世紀末 | 266(×4.3) | 829(×2.3) | 120(×2.6) |
- ( )内は現在⇒21世紀末の倍率
| 雪裡川 | SS(kt/年) | 全窒素(t/年) | 全リン(t/年) |
|---|---|---|---|
| 現在 | 34.1 | 378 | 39.8 |
| 21世紀末 | 282(×8.3) | 1260(×3.3) | 166(×4.2) |
- ( )内は現在⇒21世紀末の倍率
| 幌呂川 | SS(kt/年) | 全窒素(t/年) | 全リン(t/年) |
|---|---|---|---|
| 現在 | 14.2 | 228 | 22.4 |
| 21世紀末 | 72.9(×5.1) | 576(×2.5) | 67.3(×3.0) |
- ( )内は現在⇒21世紀末の倍率
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
下記の3点を前提とした予測結果であるため、ピーク流量や土砂・栄養塩負荷量を過大に評価した可能性があることに留意が必要である。
- 21世紀末の仮想的な1年間の日降水量を推定する際に、現在における平均的な年ではなく、特異的な大雨のあった2016年をベースとしている。
- 現在と21世紀末とで、同じ流量におけるL-Q式が不変であることを仮定している。
- 現在観測される流量の範囲で成立しているL-Q式が、21世紀末に想定される流量の範囲まで外挿できることを仮定している。
本調査の将来予測の対象外とした事項
釧路湿原の水循環には、下記の要素も影響すると考えられるが、調査期間の制約及び既存知見の不足により、本調査では考慮していないことに留意が必要である。
- 気温の変化に伴う蒸発散量への影響
- 積雪及び融雪状況の変化に伴う河川流量への影響
その他、成果を活用する上での制限事項
本調査では、釧路湿原自然再生事業において構築された水循環モデル及びL-Q式を利用している。他の湿原において同様の検討を行う場合は、こうしたモデルが必要となる。
適応オプション
釧路湿原では、釧路湿原自然再生協議会による再生・保全事業が進められており、それらのうちのいくつかは、そのまま適応策としても有効であることが分かった。土砂・栄養塩流入の抑制策として、河道の安定化、未利用農地の再湿地化、土砂調整地の整備、などが想定される。また、保水機能の向上策として、未利用農地の再湿地化による湿地面積の回復などが想定される。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 河道の安定化 | ● | ● | -※ | 計画、実施、評価に要するコストが大 | △ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 高 | |
| 未利用農地の再湿地化 | ● | ● | -※ |
|
△ | ○ | △ | △ | 短期 | 中 | |
| 土砂調整地の整備 | ● | ● | -※ |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 高 | |
| モニタリング | ● | ● | -※ |
|
△ | ◎ | ◎ | ◎ | 長期 | 低 | |
| 普及啓発 | ● | ● | -※ |
|
△ | ◎ | ◎ | ◎ | 長期 | 低 | |
- 釧路湿原自然再生事業において事例あり
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| 河道の安定化 【発生源対策】 |
釧路湿原自然再生事業において、久著呂川を対象として、本対策の実施と効果検証が行われている。久著呂川を通じて湿原へ流入する土砂を約5%低減する効果があったと見積もられている(出典:第25回釧路湿原自然再生協議会資料)。 |
| 未利用農地の再湿地化 【緩衝帯整備】 |
釧路湿原自然再生事業において、広里地区及び幌呂地区を対象として、本対策が実施されている。湿地面積の回復効果は認められている一方、土砂・栄養塩の捕捉効果は定量的には分かっておらず、効果は中とした(出典:第25回釧路湿原自然再生協議会資料)。 |
| 土砂調整地の整備 【出水時土砂捕捉】 |
釧路湿原自然再生事業において、久著呂川を対象として、本対策の実施と効果検証が行われている。久著呂川を通じて湿原へ流入する土砂を約30%低減する効果があったと見積もられている(出典:第25回釧路湿原自然再生協議会資料)。 |
| モニタリング | 釧路湿原自然再生事業において、各河川における水質調査、各施策の効果検証などが行われている。直接的な施策ではないことから、効果は低とした(出典:第25回釧路湿原自然再生協議会資料)。 |
| 普及啓発 | 釧路湿原自然再生事業において、現地ツアー、講演会などが開催されている。釧路湿原の保全には地域住民の理解と協力が不可欠である一方、直接的な施策ではないことから、効果は低とした(出典:第25回釧路湿原自然再生協議会資料)。 |