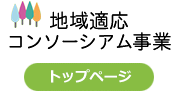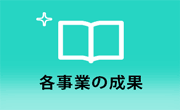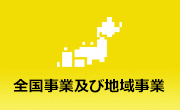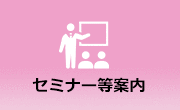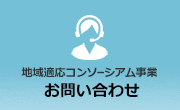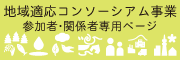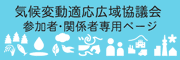気候変動による高層湿原の生物群集への影響調査
| 対象地域 | 近畿地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 先行調査 |
| 分野 | 自然生態系 |
| ダウンロード |
概要
背景・目的
高層湿原は、植物遺体等が分解されずに泥炭として堆積が進んだ結果、湿原の水面標高が周囲の地下水位標高よりも高くなった湿原である。氷河期の遺存種や貴重な動植物が生息・生育するなど、生物多様性保全の面から重要である。国内では北海道や東日本の高標高地等の冷涼地に多く、近畿地方以南では極めて稀であり、深泥池(京都市)は特に貴重な環境である。また、温暖な近畿地方においては、気候変動による影響も受けやすいと考えられる。
このような特性を持つ高層湿原は気候、水文環境、地形等の条件が微妙なバランスに保たれて形成・維持されている。気候変動に伴い、そのバランスが変化する可能性があるが、その影響に関する知見は不足している。
そこで、近畿地方にある数少ない高層湿原の一つである深泥池を対象として、気候変動による生物群集への影響を考察するとともに、適応策の検討を行った。
実施体制
| 本調査の実施者 | 株式会社プレック研究所、京都大学防災研究所、一般財団法人日本気象協会 |
|---|---|
| アドバイザー | 京都大学防災研究所 准教授 竹門康弘 京都大学防災研究所 准教授 田中賢治 |
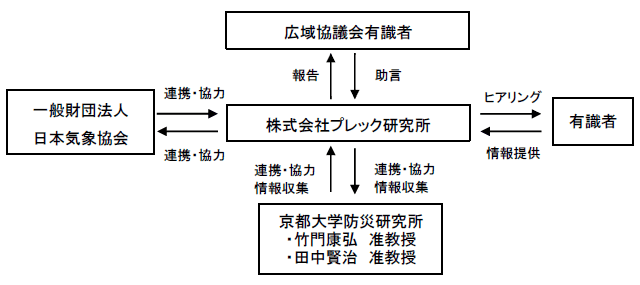
実施スケジュール(実績)
本調査では、平成29年度から平成31年度の3年間で、対象地域における影響を調査し、将来の影響評価及び適応策の検討を行った(図6.1-1)。
平成29年度に既存文献調査及び有識者ヒアリングを行い、高層湿原と気候変動に関する知見や近畿地方における湿地環境の保全の現状等についてとりまとめた。これらを基に、気候変動が高層湿原に及ぼしうる影響要因を整理し、影響評価の方向性を検討した。
平成30年度は、深泥池に水位ロガーを設置し、池の水位及び浮島地下水位の連続観測を開始した。また、異なる複数の環境において生物相調査(現地調査)を行い、深泥池における環境条件と生物相との対応関係を整理した。
平成31年度は、新たに雨量の観測を行い、深泥池の正確な雨量データを把握した。このデータを用いて水位計算モデルの改良を行い、将来の深泥池の水位の状況を予測した。水位の予測結果と、平成29年度に整理した環境条件と生物相との対応関係を照らし合わせ、気候変動が深泥池の生物群集に及ぼし得る影響を考察した。その結果を踏まえ、適応策を検討した。
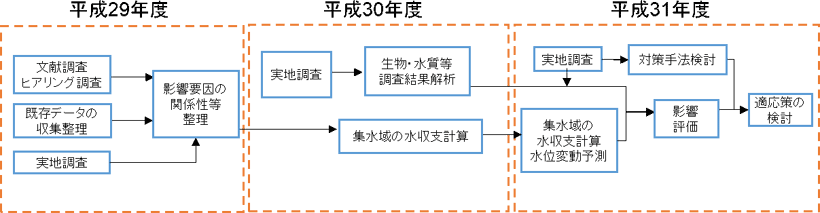
気候シナリオ基本情報
本調査で利用した気候シナリオの基本情報を表6.1-1に示す。
| 項目 | 深泥池の水位 |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | 気象研究所2㎞力学的DSデータ by創生プログラム |
| 気候モデル | MRI-NHRCM02 |
| 気候パラメータ | 気温、風速、降水量、短波放射、長波放射、水蒸気圧、気圧 |
| 排出シナリオ | RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 有り(地域) |
気候変動影響予測結果の概要
文献調査においては、主に以下のようなことが分かった。
- 深泥池の浮島上にはビュルテ(凸部)やシュレンケ(凹部)と呼ばれる微地形がモザイク状に散在し、池塘もある。こういった複雑な条件に見合った多様な植物・動物(生物群集)が存在している(深泥池七人委員会編集部会、2008)。
- ミズゴケ類が優占する湿地においては地表面に凹凸が見られ、その高低差は1~2cmであっても土壌環境の違いに大きく反映され、湿地植生を決める要因にもなる(原口、2010)。
ヒアリングにおいては、主に以下のようなことが分かった。
- 湿原において水位が低下すると、夏季の渇水期に泥炭が乾燥し、ススキが侵入・定着するようになり、湿原の陸化が進む。
- 湿地の環境は水文と植物と土壌の3要素が最も重要であり、最低限、地下水位と植生がモニタリングできると良い。
- 泥炭が形成され溜まるのは湿性植物がよく生育する温暖期であり、湿原形成の上では水環境や地形変化の影響が大きい。
影響予測を行った結果、主に以下のようなことが分かった。
- 今世紀末において、深泥池の水位低下が起こる頻度が著しく増加し、水位低下の程度も現在では起こらないような程度にまで達する可能性があることが予測された。
- 水位の低下に伴い、浮島地下水内の溶存酸素濃度の低下、浮島上に水面を要するシュレンケ(凹部)の減少、ビュルテ(凸部)の乾燥化を起点とした陸地化、ビュルテの冷涼環境の喪失等といった環境の変化が生じ、水生生物にも影響が及ぶと予想された。
ア. 深泥池の水位
今世紀末は現在よりも明らかに渇水の頻度・程度とも増加している。年によっては現在ではほとんど見られないような程度の水位低下が起こるようになる(図6.1-3参照)。
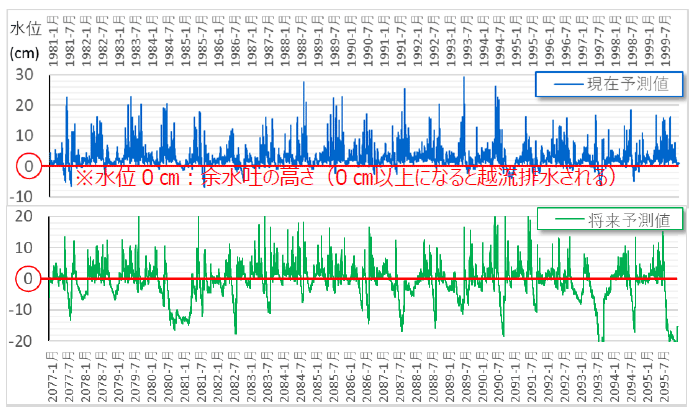
イ. 深泥池の生物群集
将来、上記のような渇水頻度・程度となった場合に、水生生物の生息場に起こりうる影響のイメージ図を図6.1-4に示す(イメージ図であり、実際には、深泥池の水位と比較し、浮島の地下水位の低下の方が渇水の程度は弱いと考えられる)。水位の低下により、環境が変わることで、生物群集にも影響が及ぶことが予想された。
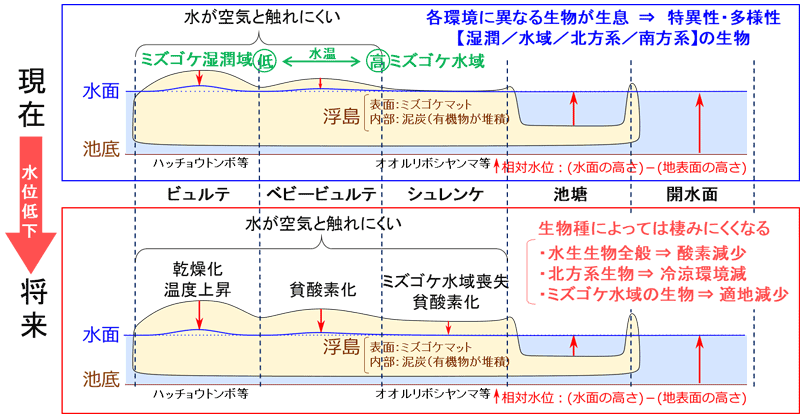
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
本調査では、気候変動による深泥池の水位変化と、水位変化が生物群集に与える影響を対象とした。生物群集については、水生生物(浮島を形成するミズゴケや泥炭の隙間の水分内に生息する生物を含む)を対象とした。
本調査の将来予測の対象外とした事項
深泥池の水生生物の生息適否には、下記の要素が影響すると考えられるが、本調査において気候変動予測を実施するにあたり、下記の影響は考慮していないことに留意が必要である。
- 浮島上の微地形(凹凸構造)そのものの分布の変化
- 浮島の形状の変化
その他、成果を活用する上での制限事項
生物相調査において多種の生物種が確認されているが、種ごとの生態・生理に関する知見は限られており、深泥池における調査結果から生物と環境条件との関係を考察している。
適応オプション
適応オプションを表6.1-2に整理する。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| ①環境モニタリング | ● | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ○ | △ | ◎ | N/A | 中 |
| ②水文環境の改善 | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | △ | △ | △ | 長期 | 高 | |
| ③生息場の保全 | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 中 | |
| ④水質の維持・改善 | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 中 | |
| ⑤人為的管理/利用文化の活用 | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| ⑥複合的な要因の排除 | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | △ | △ | △ | 長期 | 中 | |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 |
|---|---|
| ①環境モニタリング | 水質調査や生物調査などがすでに行われており、これらの取組みとの連携を含めた実施体制の検討が必要。 |
| ②水文環境の改善 | 深泥池はため池という側面もあり稀に取水されることもあるため、特に水不足時は水利用の観点にも留意が必要 |
| ③生息場の保全 | 生息する生物の整理・生態に関する知見が必ずしも十分ではないためこれらに関する基礎的なデータの収集も重要 |
| ④水質の維持・改善 | 現状では降雨時の路面排水による影響が大きく、住宅地側からの深泥池への流入は特に留意が必要 |
| ⑤人為的管理/利用文化の活用 | 天然記念物との調整のうえ、一部であるが既に活動が始められつつある |
| ⑥複合的な要因の排除 | 外来生物(魚類・植物等)やニホンジカによる影響など既に起こっている喫緊の課題がありこれらへの対応が必要 |