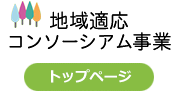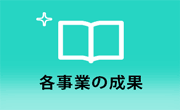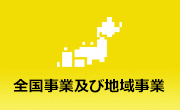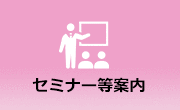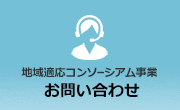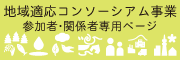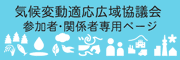気候変動による有明海・八代海における漁業及び沿岸生態系への影響調査
| 対象地域 | 九州・沖縄地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 先行調査 |
| 分野 | 農業・林業・水産業 |
| 備考 | 九州・沖縄地域の気候変動影響に関する調査(平成29年度開始調査) |
| ダウンロード |
概要
背景・目的
近年、気候変動に伴い有明海及び八代海の沿岸、干潟、河口域の海水温は上昇傾向にある。
水温上昇は潮位、DO等の漁場環境や沿岸生態系に影響を与えることから、沿岸域の水産資源の減少や生物多様性の損失の一因として懸念されている。また、気候変動は、局所的な集中豪雨、降水量の増加等を引き起こし、河川流域等から土砂、流木等を有明海・八代海に流入させ、流し網漁業、採貝漁業、海苔養殖業など、水産業に直接的な被害をもたらす。
さらに、有明海・八代海には、トビハゼやシオマネキ等が多数生息する泥質干潟、アサリ等の二枚貝類が豊富に生息する砂質干潟の両方が存在し、それぞれ独特の生態系が成立している。各干潟は有明海・八代海特有の希少生物の生息場であるとともに、水質浄化に大きく役立っており、これらへの気候変動の影響が懸念される。
しかし、気候変動による有明海・八代海の漁業及び沿岸生態系への影響と対応等について検討した事例はほとんどない。
本調査は、海水温、塩分、水位等の現況について現地調査と既存文献により把握するとともに、既存調査・文献等をもとに漁業対象種、干潟生物の分布と生息環境との関係を検討した。さらに、有明海・八代海における漁業及び沿岸生態系について、気候変動が及ぼす影響の有無とその程度を検討し、水産業の継続及び干潟生態系保全のための適応策を検討した。
実施体制
| 本調査の実施者 | 一般財団法人 九州環境管理協会 |
|---|---|
| アドバイザー | 国立研究開発法人水産研究・教育機構 西海区水産研究所 有明海・八代海漁場環境研究センター 主幹研究員 松山幸彦 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所 湾空港技術研究所 海洋情報・津波研究領域 海洋環境情報研究グループ 井上徹教 九州大学農学研究院 資源生物科学部門 准教授 望岡典隆 熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 教授 逸見泰久 |
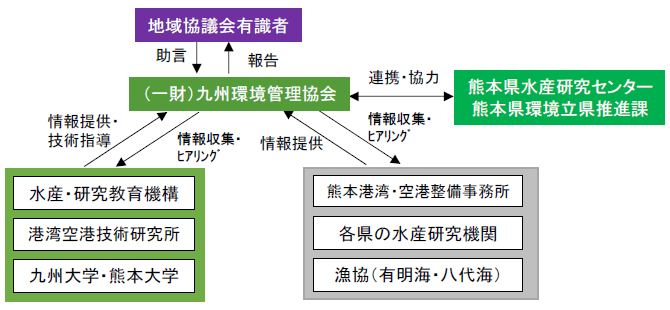
実施スケジュール(実績)
平成29、30年度、令和元年度の3カ年で実施した。
平成29年度は、近年の気象変化、有明海・八代海の漁業や魚類等の生態・生活史等の情報を収集・整理し、気候変動の影響をうける漁業対象種13種(以下、調査対象種という)を抽出した。
平成29~30年度は、有明海・八代海の海域、干潟域の海水温を把握するために、熊本県地先の表層水温の連続観測を実施した。
平成30年度、令和元年度は、伊勢湾シミュレータを用いて21世紀末の水温・塩分・水位を予測し、調査対象種への影響、適応策もしくは提言を検討した。さらに、令和元年度は、八代海湾奥部のモデル地区で、希少貝類・カニ類の分布と生息する地盤高を調査した。
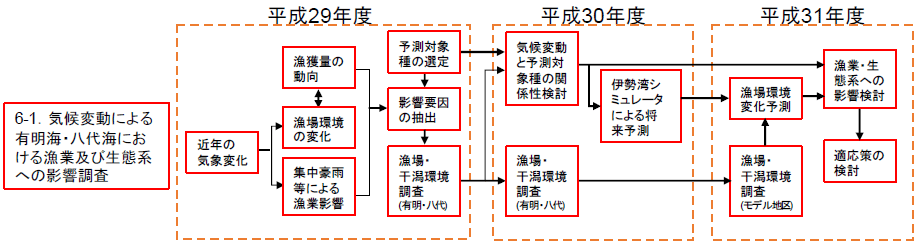
気候シナリオ基本情報
「海洋近未来予測力学的DSデータ」の気候モデルを用いて、RCP2.6、RCP8.5の場合の21世紀末について、計2パターンの予測を行った(表 2.1-1)。
| 項目 | 対象種の収穫量、漁期、分布域など | |
|---|---|---|
| 気候シナリオ名 | 気象研究所2km力学的DSデータ by 創生プログラム | 海洋近未来予測力学的DSデータ by SI-CAT |
| 気候モデル | MRI-NHRCM02 | MRI-CGCM3 |
| 気候パラメータ | 気温、降水量、日射量、雲量、相対湿度、風速、比湿 | 海水温、塩分(気温、降水量、日射量、雲量、相対湿度、風速、比湿はRCP2.6のみ) |
| 排出シナリオ | RCP8.5 | RCP2.6、RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀末 | |
| バイアス補正の有無 | 有り(地域) | 有り(地域) |
気候変動影響予測結果の概要
本業務で対象にした13種を表 2.1-2に示す。調査対象種のうち、水温・塩分と成長との関係に関する情報・知見があり、気候変動影響について定量的に予測した種は、ノリ養殖、ワカメ、シャトネラ赤潮の3種であった。残りの10種については、定性的に予測した。
| 分野 | 調査対象種 |
|---|---|
| 漁業 | ノリ、ワカメ、ブリ・マダイ |
| ヒラメ・カレイ類、ムツゴロウ、マアナゴ、ハモ・サワラ・ハタ類、アサリ、ハマグリ、シャトネラ赤潮 | |
| 生態系 | 希少貝類・カニ類、藻場全般 |
| 人への危害 | 南方系フグ・ヒョウモンダコ |
水温・塩分と成長との関係に関する知見があるもの
ノリ養殖の予測の結果、21世紀末(RCP2.6)の場合、採苗開始は11月となり、11月末の収穫は見込めないため、漁期が短くなり、収量が減少するものと予測された。また、11、12月の葉体の日増加率は、図 2.1-4に示すように、現在の0.98~099と若干減少し、1月以降は現在よりもわずかに増加するものと予測された。
21世紀末(RCP8.5)の場合、採苗開始は12月となり、漁期も2月までと短くなるため、収量が減少するものと予測された。また、11~1月の葉体の日増加率は、現在に対して0.93~0.97に減少し、2月は現在よりも若干増加するものと予測された。
色落ち原因種である珪藻類の増殖可能期間は、21世紀末(RCP2.6)、21世紀末(RCP8.5)ともに、ノリ養殖の漁期10~3月に増殖可能な水温であり、まとまった降雨がみられると、色落ちが発生しやすくなる可能性がある。
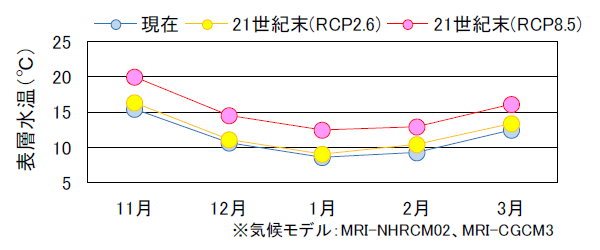
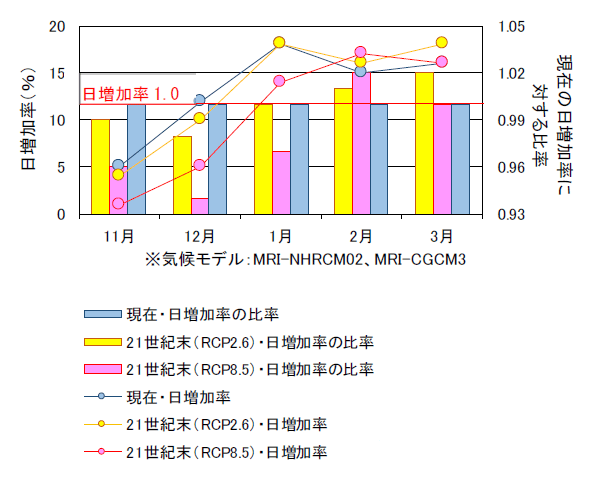
水温・塩分と成長との関係に関する知見が少ないもの
対象種13種のうち、水温・塩分と生長との関係に関する知見が少なく、生息上限・下限値などにより定性的に予測した種は、ブリ・マダイ養殖、ヒラメ・カレイ類、ムツゴロウ、マアナゴ、ハモ・サワラ・ハタ類(キジハタ)、アサリ、ハマグリ、藻場であった。
ブリ・マダイ養殖、ハモは、生息期間・場所を現在と21世紀末(RCP2.6、RCP8.5)の水温予測結果を比較し、影響を予測した。
その結果、ブリ・マダイ養殖は、図 2.1-5に示すように21世紀末(RCP2.6)の場合は8月に、21世紀末(RCP8.5)の場合は7~9月に成長上限水温に近い水温になるため、成長が遅れ、出荷時期も遅れる可能性がある。
ハモは、図 2.1-6に示すように21世紀末(RCP2.6)の場合、現在と同じく2月に摂餌下限水温を下回るが、21世紀末(RCP8.5)の場合、1~2月に摂餌下限水温を上回り、摂餌可能な期間が長くなるため、生息量、漁獲量が増加する可能性がある。
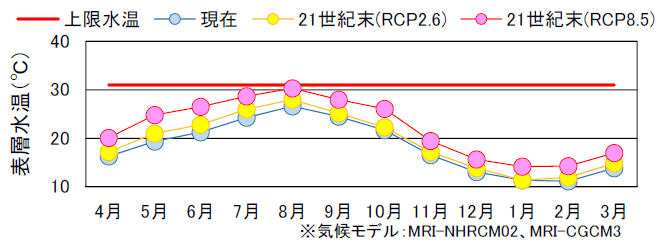

水温・塩分と成長との関係に知見がなかったもの
対象種13種のうち、定性的に予測した種は、希少貝類・カニ類、南方系フグ類・ヒョウモンダコであった。
希少貝類・カニ類は、八代海湾奥部のモデル地区で実施した現地調査により、潮間帯・潮上帯の希少種の生息範囲を把握し、現在と21世紀末(RCP2.6、RCP8.5)の水位の予測結果から生息可能域を予測した。
モデル地区では、図 2.1-7に示すように21世紀末(RCP2.6)で平均水位が0.3~0.4m、21世紀末(RCP8.5)で0.7~0.8m高くなる。
低地盤域に分布する貝類・カニ類は、21世紀末(RCP2.6)、21世紀末(RCP8.5)ともに、現在よりも高地盤域へ移動することができるが、護岸沿いの高地盤域に分布する貝類・カニ類は、現在の分布域よりも高い場所が堤防等によって分断され、移動することができない。また、水位上昇により海水の冠水時間が長くなり、干潟域の底泥中の塩分が上昇するため、生息場所となっている塩沼地植物群落が衰退し、これらの種は生息できなくなる可能性がある。

活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
調査対象種について、漁獲量、水質等の現地測定データから関係性を把握した。このうち、関係性がみられる種は、既存文献等から温度、塩分の成長式を作成し、有明海・八代海モデルでの水温・塩分の予測結果をもとに、定量的に予測・評価した。一方、関係性がみられず、既存文献等で温度、塩分の成長式が作成できない種は、現在、21世紀末の水温・塩分変化から定性的に予測・評価した。
本調査の将来予測の対象外とした事項
調査対象種の予測にあたっては、水温・塩分のほかに、水質の栄養塩濃度や底質によっても生息・生育の可否が決まる。また、外海から侵入し、対象海域を利用する種は、外海での生息条件によって有明海・八代海での生息状況が異なる。
本調査では、水温・塩分変化に伴う予測を対象としており、栄養塩濃度や底質、外海での生息条件については対象外とした。
その他、成果を活用する上での制限事項
調査対象種の予測にあたっては、水温・塩分以外の生息条件(栄養塩濃度や底質)の変化がないことを前提に影響予測を実施した。
また、対象種のうち、外海から進入し、有明海・八代海を利用する種については、外海での変化がないことを前提に影響予測を実施した。
適応オプション
調査対象種の漁獲量の維持、生息場の保全に関する適応オプションは、表 2.1-3に示すとおりである。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 適応オプション検討の基盤となる資源・生態情報、環境モニタリングの継続(全13種対象) ※水温変化に伴う漁獲の減少、分布の変化等に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 漁場形成予測モデル・閲覧システムの開発、漁業者への注意喚起(希少貝類・カニ類を除く12種) ※水温変化に伴う漁獲の減少、分布の変化等に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 母藻投入、種苗投入等の天然漁場の回復、食害生物の駆除(ワカメ、藻場、アサリ、ハマグリ) ※水温・水位変化に伴う漁場の縮小、漁獲量の減少、食害生物の定着に伴う生息適地の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 資源回復・定着に向けた漁場整備・保全(マアナゴ、ハモ・サワラ・ハタ類、アサリ、ハマグリ、希少貝類・カニ類) ※水温・水位変化に伴う漁場の縮小、漁獲量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 親貝の保護、作澪、覆砂材・基質・網袋等による着底促進、浮遊幼生ネットワークの解明と幼生着底促進技術の開発(アサリ、ハマグリ) ※夏場の水温上昇に伴う親貝の斃死、漁獲量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 人工湧昇流発生構造物、鉛直混合促進構造物設置による成層の解消(ヒラメ・カレイ類、マアナゴ、シャトネラ赤潮) ※夏場の水温上昇に伴う漁獲量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | △ | △ | △ | 長期 | 高 | |
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 新規赤潮防除材の開発(シャトネラ赤潮) ※夏場の水温上昇に伴う赤潮の発生頻度の増加に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 高水温耐性種・適応種の研究・開発・普及、人工種苗の活用(シャトネラ赤潮、希少貝類・カニ類を除く11種) ※水温上昇による漁期の短縮、成長不良、漁獲量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 養殖スケジュールや漁期・漁場・漁法、対象種の見直し(シャトネラ赤潮、希少貝類・カニ類を除く11種) ※水温上昇による漁期の短縮、成長不良、漁獲量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| 養殖の協業化(養殖施設の共同使用等)、陸上養殖(ノリ養殖、ブリ・マダイ養殖) ※水温上昇による漁期の短縮、生産量の減少に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | △ | △ | ◎ | 長期 | 高 | |
| 類似種等の情報発信、注意喚起、水揚げ市場での正常な判断と流通の阻止(南方系フグ類・ヒョウモンダコ) ※夏場の水温上昇に伴う有毒種の北上、交雑種の生息に対するオプション |
● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | △ | ◎ | △ | 長期 | 中 | |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方 | 出典 |
|---|---|---|
| ①適応オプション検討の基盤となる資源・生態情報、環境モニタリングの継続 | 普及率の表記なし。 実施事例は多数あり、測定結果から採苗開始、餌止め時期等の適正時期を見極めるなど、効果発現までが短期となる事項もある。一方、適応策の検討は、データの蓄積、気候変動やそれに伴う漁場変化の監視が必要である。効果発現までの時間は長期とした。 各県から発行された「気候変動影響と適応取組み」に関する資料には、定期的なモニタリングの継続の重要性が明記されている。また、気候変動による影響の検討は、影響の程度を定量的に評価できる対象種は限られている。影響を定量的に検討するためには、地先、各県で測定項目、頻度等の精度が統一された現地データ、情報の蓄積が必要である。 |
「気候変動に対応した漁場整備方策に関するガイドライン」水産庁漁港漁場整備部、平成29年6月 「宮城県地球温暖化対策実行計画」宮城県、平成30年10月 「三重県の気候変動影響と適応のあり方について」三重県、平成28年3月 |
| ②漁場形成予測モデル・閲覧システムの開発、漁業者への注意喚起 | 普及率の表記なし。 実施事例は多数あるが、適応策の検討は、データの蓄積、気候変動やそれに伴う漁場変化の監視が必要である。減少要因の解明、適応策の検討は、効果発現までの時間は長期とした。 各県から発行された「気候変動影響と適応取組み」に関する資料には、定期的なモニタリングの継続と、環境変化を予測する研究の取組み、閲覧システムの開発の重要性が明記されている。 |
「気候変動に対応した漁場整備方策に関するガイドライン」水産庁漁港漁場整備部、平成29年6月 「静岡県の気候変動影響と適応取組方針」静岡県、2019年3月 「千葉県の気候変動影響と適応の取組方針」千葉県、平成30年3月 |
| ③母藻投入、種苗投入等の天然漁場の回復、食害生物の駆除 ④資源回復・定着に向けた漁場整備・保全 ⑤親貝の保護、作澪、覆砂材・基質・網袋等による着底促進、浮遊幼生ネットワークの解明と幼生着底促進技術の開発 ⑥人工湧昇流発生構造物、鉛直混合促進構造物設置による成層の解消 |
普及率の表記なし。 漁場整備、人工湧昇流発生構造物の設置は短期であるが、生物の定着、環境の安定化には時間がかかり、モニタリングも必要である。効果発現までの時間は長期とした。 気候変動に適応した漁場整備、有機物削減等の対応可能な複合要因の除去など、並行して実施することも明記されている。 |
「気候変動に対応した漁場整備方策に関するガイドライン」水産庁漁港漁場整備部、平成29年6月 「漁場環境改善技術導入の手引き」水産庁 |
| ⑦新規赤潮防除剤の開発 | 普及率の表記なし。 防除剤散布後の赤潮消滅など、効果発現までの時間は短期であるが、防除剤の改良・新規開発には、養殖魚類、環境に及ぼす影響など、毒性試験、モニタリングが必要である。効果発言までの時間は長期とした。 |
「赤潮被害を軽減する~赤潮防除剤開発試験~」鹿児島県水産技術開発センター |
| 適応オプション | 適応オプションの考え方 | 出典 |
|---|---|---|
| ⑧高水温耐性種・適応種の研究・開発、人工種苗の活用 ⑨養殖スケジュールや漁期・漁場・漁法、対象種の見直し |
普及率については表記なし。 いずれの種においても、高水温耐性種・種苗の開発・育種は有効であり、すでに進められている種もある。しかし、品質を確保した耐性種、種苗は未開発のものも多く、引き続き開発・育種が必要である。したがって、効果発現までの時間は長期とした。また、気候変動に適応した漁期・漁場・漁法、漁獲対象種の見直しが必要。漁業者との合意形成、漁業調整規則の改正も必要。 |
「気候変動に対応した漁場整備方策に関するガイドライン」水産庁漁港漁場整備部、平成29年6月 「温暖化に負けない魚類養殖を目指せ-水温上昇に対応する飼育技術の開発-」安藤忠(北海道区水産研究所) |
| ⑩養殖の協業化(養殖施設の共同使用等)、陸上養殖 | 普及率については表記なし。 実施に伴い、気候変動への適応に直結するものではないが、コスト削減、作業効率の向上、品質の向上により漁獲量、単価の安定化が図れる。施設・組織の構築は、効果発現までの時間が短期であるが、漁業者間での生産性の方針、調整については協議が必要となる。したがって、効果発現までの時間は長期とした。 |
「福岡県有明海におけるノリ養殖の協業動向と展開方向-協業の動向と共同乾燥組織形成の課題-」篠原満寿美ほか、福岡水海技セ研報第29号、2019 年3月 「有明海漁連協業化推進委員会資料」 |
| ⑪類似種等の情報発信・注意喚起、水揚げ市場での正常な判断と流通の阻止 | 普及率については表記なし。 混入率の確認等については効果発現までの時間は短期であるが、類似種を正確に、かつ簡易な方法で同定できるシステムの開発には時間を要する。したがって、効果発現までの時間は長期とした。また、分布・確認件数等の情報が少ないが、気候変動により有害種が北上する可能性があり、食用への回避、安全性の確保のための対策が必要である。 |
「食品衛生検査所レポート」福岡市 |