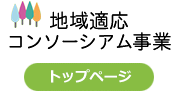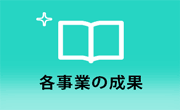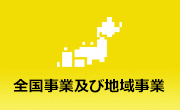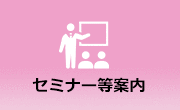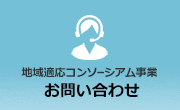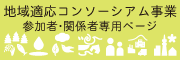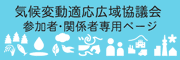気候変動による水害リスクの評価
| 対象地域 | 九州・沖縄地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 先行調査 |
| 分野 | 自然災害・沿岸域 |
| ダウンロード |
概要
背景・目的
九州地域・沖縄地域には、水稲など農作物の栽培を目的としたため池が多く分布している。その多くは江戸時代に築造されたものと推測され、老朽化が進んでいる。
近年、気候変動などの影響で集中豪雨が頻発する傾向で、住宅や農地などへ大きな被害が発生している。ため池の数が福岡県内で最も多く、ため池等の水害リスクが比較的多い北九州市をモデルとして、気候変動を踏まえたため池等の水害リスクの評価手法の検証及び適応策を検討した。
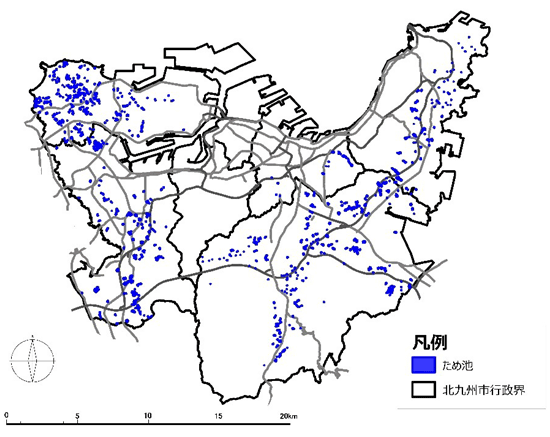
図 3.1-1 調査実施場所
実施体制
| 本調査の実施者 | 一般財団法人九州環境管理協会 |
|---|---|
| アドバイザー | 国立大学法人九州大学大学院平松和昭教授 農研機構農村工学研究部門 吉迫宏氏 |
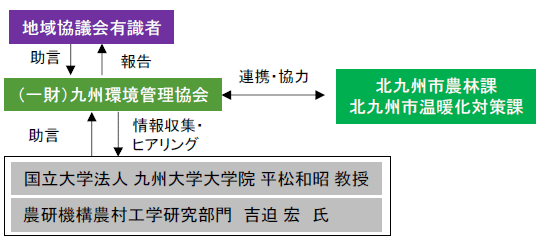
実施スケジュール(実績)
平成29年度は、北九州市内のため池の情報の収集・整理、GISデータ化、広域的な水害リスク解析を行った。平成30年度は、簡易解析モデルを用いた水害リスク解析、適応策の検討を行った。平成31年度は、引き続き簡易解析モデルを用いた水害リスク解析を行うとともに、適応策の検討を行った。
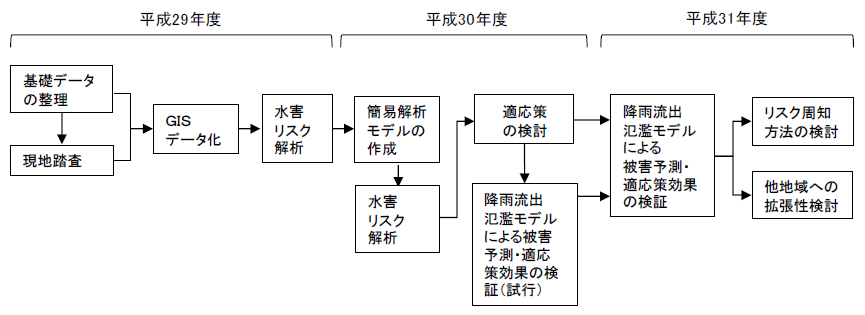
気候シナリオ基本情報
| 項目 | 洪水時の流出流量 | |
|---|---|---|
| 気候シナリオ名 | 地球温暖化対策に資するアンサンブル気候予測データベース(d4PDF) | |
| 気候モデル | MRI-NHRCM20 | |
| 気候パラメータ | 降水量 | |
| 排出シナリオ | RCP8.5(4度上昇) | |
| 予測期間 | 21世紀末 | |
| バイアス補正の有無 | 無し | |
気候変動影響予測結果の概要
21世紀末(RCP8.5)には、設計指針の整備水準を満たしていないため池が、約4割増加すると予測された。
設計指針の整備水準を満たしていないため池のうち、下流影響度が他のため池と比べて特に高かったため池を水害リスクの高いため池として選定した。その結果、北九州市内のため池のうち、2箇所(A池、B池)を選定した。そのうち、水害リスクが高いA池について適応策として「低水位管理」及び「スリット設置」を実施した場合の効果を予測した結果、適応策を実施することで、200年確率の大雨においても、堤体の上流端からの越流が生じないと予測された。
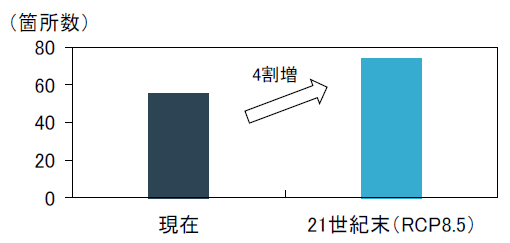
図 3.1-3 設計指針の整備水準を満たしていないため池の増加度合
| ため池 名称 |
確率 降水量 |
現在 | 21世紀末(RCP8.5) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適応策 なし |
適応策あり | |||||
| 低水位管理(-0.5m) | 低水位管理(-1.0m) | スリット設置 | ||||
| A池 | 30年 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 50年 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 100年 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 200年 | × | × | ◯ | ◯ | ◯ | |
- 1.「◯」:越流が発生しない 「×」:越流が発生する
- 2.低水位管理は、満水位よりも0.5m下げた場合と1.0m下げた場合を予測した。
- 3.気候モデル:MRI-NHRCM20 排出シナリオ:RCP8.5
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
整備水準を満たしているかどうかの評価は、ため池の設計で用いる手法に基づいて、洪水流入に伴う越流発生を指標として推定した。
本調査の将来予測の対象外とした事項
本調査では、ため池貯水位の増加に伴うため池堤体の決壊は考慮していない。また、流木や土砂の流入による影響は考慮していない。
その他、成果を活用する上での制限事項
一般的にダムで行われている水文観測データがため池にはないため、ため池への流入量について、パラメータ等に文献値を用いざるをえない。当然のことながら、流出特性はため池毎に異なることから、長期にわたる水文観測や各種パラメータ調査を行うなど、精査が必要である。
適応オプション
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | |||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | |
| ため池堤体の嵩上げ・浚渫 | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | △ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 洪水吐スリットの設置 (緊急放流孔) |
● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | △ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 降雨前の事前放流による低水位管理 | ● | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 |
| 期別毎の低水位管理 | ● | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 |
| ため池ストック管理の適正化 | ● | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 |
| 浸水想定区域図の作成 | ● | 普及が進んでいる |
|
◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| ため池ハザードマップの作成 | ● | 普及が進んでいる |
|
◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| ため池防災支援システムの活用 | ● | 普及が進んでいる |
|
◎ | ◯ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 水位計等による監視体制の整備 | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◯ | △ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 適応オプション | 適応オプションの考え方 |
|---|---|
| ① ため池堤体の嵩上げ・浚渫 |
<ため池の洪水調節機能を強化する方法> 嵩上げ、浚渫ともに既存技術で対応可能である。嵩上げの場合、工法によっては新たな用地買収が発生する。また、浚渫の場合、浚渫土砂の処分費用が新たに発生する。普及率に関しての情報はない。 |
| ② 洪水吐スリットの設置(緊急放流孔) |
<ため池の洪水調節機能を強化する方法> ため池の洪水調節機能を強化する方法として、既存事例がある。既存の技術で対応可能であり、施設の大規模な改修を伴わないため低コストである。スリットの大きさは、下流排水路の流下能力を考慮したものとする。堰板を用いる場合は、作業員が一人で外せる程度の規格(0.5m×0.5m)とする。なお、北九州市では洪水吐スリット(緊急放流孔)を洪水吐改修の条件としている。 |
| ③ 降雨前の事前放流による低水位管理 |
<ため池の洪水調節機能を強化する方法> 豪雨の発生が予測される際、ため池の貯留水を事前に放流し、空き容量を確保する方法。施設の改修を伴わないソフト対策として、普及率に関しての情報はないが、多くの実施事例がある。既存の設備で対応可能であり、設備に係る追加費用は不要である。実施にあたっては、水位低下開始のタイミング、営農面への配慮、関係者間の情報共有、管理規定等の作成が必要である。降雨波形が後方分布型や2山型などの場合は、低水位管理でも対応が難しいことがある。 |
| ④ 期別毎の低水位管理 |
<ため池の洪水調節機能を強化する方法> ③とほぼ同様の手法であるが、降雨前に水位を低下させる即時的な管理ではなく、かんがい期、非かんがい期等の期別毎に水位を設定して管理する手法である。普及率に関しての情報はないが、多くの実施事例がある。上記同様に設備に係る追加費用は不要である。 |
| ⑤ ため池ストック管理の適正化 |
<ため池の治水機能を活用する方法> ため池は結果的に「治水機能」を発揮していることもある。農業上の利用度が低いことに加え、老朽化が著しく決壊等の危険度の高いため池については、ため池の統廃合や廃止を検討する。その際には、ため池が洪水を一次貯留するなど下流域への被害を軽減することもあることを踏まえ、機能を吟味し、適正化を図る必要がある。普及率に関しての情報はない。 |
| ⑥ 浸水想定区域図の作成 |
<ため池の緊急時の迅速な避難行動につなげる手法> 普及率に関しての情報はないが、農林水産省において全ての防災重点ため池について浸水想定区域図を整備するように推進している。 地域において緊急時の迅速な避難行動につなげるためには、市町村が避難に係る判断に必要な情報を平常時から地域住民等に提供しておく必要がある。 |
| ⑦ ため池ハザードマップの作成 |
<ため池の緊急時の迅速な避難行動につなげる手法> 令和元年度5月末現在、287の市町村のため池ハザードマップをホームページ上で閲覧可能である。新たな基準により都道府県で再選定した防災重点ため池63,722箇所について、決壊した場合の影響度に応じて優先順位を付けてハザードマップの作成等を実施していくことになっている。地域において緊急時の迅速な避難行動につなげるためには、市町村が避難に係る判断に必要な情報を平常時から地域住民等に提供しておく必要がある。 |
| ⑧ ため池防災支援システムの活用 |
<ため池の緊急時の迅速な避難行動につなげる手法> 豪雨・地震時に決壊のおそれのあるため池と被害の危険度をリアルタイムで予測・表示するシステムである。迅速な情報収集・共有に活用できるシステムであることから、国、都道府県、市町村が一体となって活用していくことを推進している。 |
| ⑨ 水位計等による監視体制の整備 |
<ため池の緊急時の迅速な避難行動につなげる手法> 普及率に関しての情報はない。特に影響度の大きなため池については、豪雨や地震時等にため池の状況を速やかに把握し、適切な判断や行動につなげられるよう計画的に水位計等の管理施設の整備を推進している。 設置費用は、北九州市(福岡方式)では約50万円、他の自治体では150~250万で設置している。 |