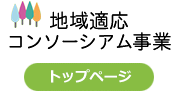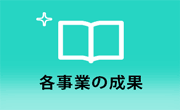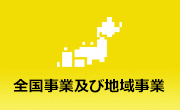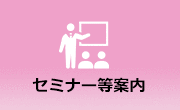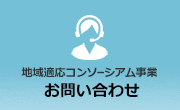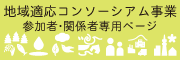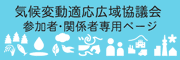湿地環境に関する影響調査【新潟市】
| 対象地域 | 関東地域 |
|---|---|
| 調査種別 | 率先調査 |
| 分野 | 水環境・水資源 自然生態系 |
| ダウンロード |
概要
背景・目的
佐潟は、ラムサール条約湿地に登録されており、オニバス等の水生植物をはじめ、希少種が多数生育・生息するなど、生物多様性を保全する上で重要な湖沼である。近年ではアオコが発生するなど水質の悪化が問題となっている。今後、気候変動の影響による水収支の変化により、更なる水質の悪化や水生植物へ与える影響が懸念されている。
本調査では、佐潟の水収支を明らかにし、気候変動による佐潟の水質、水生植物等、湿地環境への影響を予測し、適応策を検討した。

実施体制
| 本調査の実施者 | パシフィックコンサルタンツ株式会社 |
|---|---|
| アドバイザー | 新潟大学 准教授 志賀 隆 |
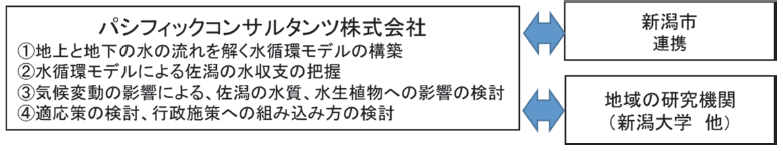
実施スケジュール(実績)
本調査の実施スケジュールを下図に示す。調査は2ヶ年で実施した。
平成30年度に、資料・データの収集を行い、三次元水循環解析モデルを構築した。過年度での地下水位や放流量、湖面水温の実測データを用いて、モデルの再現性を確認した。また、既往調査から物理的条件の水生生物への影響を整理し、影響予測手法について検討した。平成31年度は、三次元水循環解析モデルの予測結果から、水質や生物への影響を検討・評価した。また、適応策の検討にあたっては、既往の取組や、地元関係者へのヒアリングなどを踏まえて検討した。
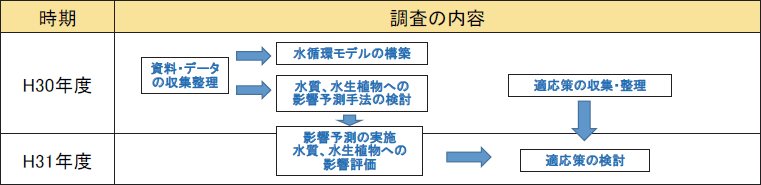
気候シナリオ基本情報
本調査において使用した気候シナリオは下表に示すとおりである。
気候モデル(1つ)×RCP(2つ)×予測期間(現在1つ、将来気候2つ)について予測を行った。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 気候シナリオ名 | NIES統計DSデータ |
| 気候モデル | MRI-CGCM3 |
| 気候パラメータ | 気温、降水量、日射量、湿度、風速 |
| 排出シナリオ | RCP2.6、RCP8.5 |
| 予測期間 | 21世紀中頃、21世紀末 |
| バイアス補正の有無 | 有り(全国) |
気候変動影響予測結果の概要
本調査において、資料や現地データの収集整理とともに、地元関係者へのヒアリングを行い、予測結果および適応策の検討にあたっての基礎資料とした。
各検討において得られた結果を以下に示す。
【文献調査】
- 沈水植物は、水質の悪化とともに1990年代以降は激減してしまった。
- オニバスの消長は、成長初期段階での光条件により影響を受けるが、それが水質や水位条件に左右される。夏場の水位が低く保たれていることが重要である。
- ハスも近年は衰退傾向にあり、ここ数年は佐潟下潟ではほとんどみられていない。他地域の事例より、底泥の悪化が顕著であることが原因となっている可能性がある。
- 既往の水質調査結果より、水温が30℃を超えるとクロロフィルaの値が高くなる。
【地元関係者ヒアリング】
- かつては佐潟の周辺の一面に水田が広がり、1年に一度はその耕作のために佐潟の水を入れ替えていたため、底泥がさらわれ、水質も改善されていた。潟普請も行われていた。
【影響予測結果】
- 三次元水循環解析モデルによる解析によって、将来、佐潟の湖面水温が、アオコ発生が見られるようになる30℃を超える頻度が現在よりも高くなることが予測された。
- 三次元水循環解析モデルによる解析によって、将来、佐潟に流入する湧水量等、佐潟の水収支については、現在と比べても大きく変化しないと予測され、将来の環境変化については、湖面水温上昇による水質変化の影響が大きいことが考えられる。
水温上昇の影響
水温上昇によって、アオコ(植物プランクトン)の発生頻度が現在よりも多くなり、水中光量減少を招くと考えられる。水中光量が減少すると、沈水植物が衰退する(現在も沈水植物は限られた種しか生育していない)。
水中光量の減少と、水質悪化による底質悪化が進行すると、ハス、オニバスの発芽後の初期成長に悪影響を及ぼし、これらの植物も衰退すると推察される(現在も、ハス、オニバスは衰退が著しい)。
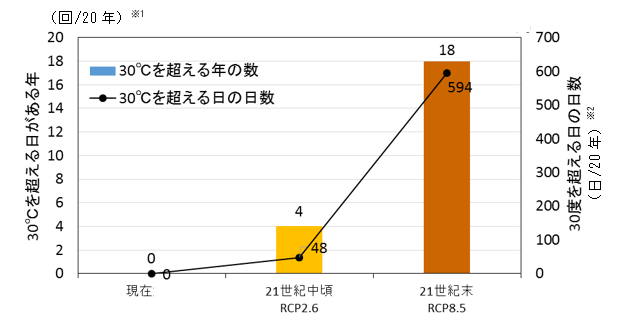
- 1:20年間のうち水温が30度を超える日がある年の回数
- 2:20年間のうち水温が30度を超える日数
水収支の予測と影響
水収支として佐潟への重要な流入水である湧水量を予測した。5~7月の湧水量は、21世紀中頃(RCP2.6)、21世紀末(RCP8.5)ともに20ヶ年50%値で約50万m3と予測され、現在の約47万m3に対して変化量は小さく、最大値・最小値の変化も小さい。
将来の環境変化については、水収支の変化による影響よりも、水温上昇の影響が大きいと考えられる。
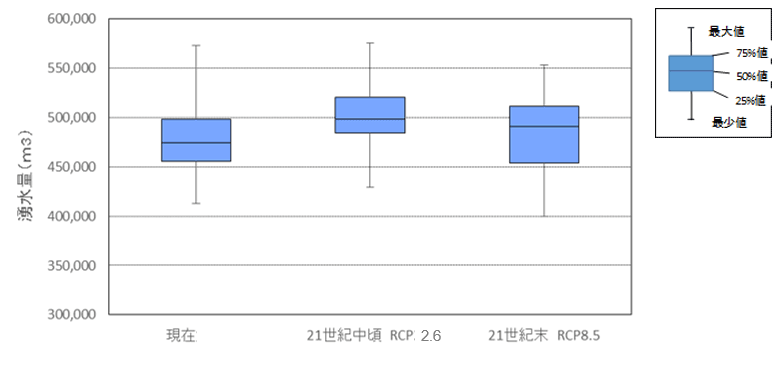
活用上の留意点
本調査の将来予測対象とした事項
本調査では、地下水を含めた佐潟の水収支と湖面水温について将来予測を行った。
本調査の将来予測の対象外とした事項
本調査では、湖水質(アオコの原因である植物プランクトンや、植物プランクトンの栄養である窒素、りん)については予測を行っていない。植物プランクトンの異常増殖により発生するアオコについては、水収支や水温の変化だけでなく、降雨に伴う流域からの窒素やりんの流入や湖底に堆積した底泥からの窒素やりんの溶出によっても影響を受けることに留意が必要である。
その他、成果を活用する上での制限事項
成果の活用上留意すべき点としては、現状における佐潟での水生植物と環境要素の応答関係は十分に解明されておらず、引き続き情報収集や知見蓄積を継続し検討を重ねる必要がある。
適応オプション
本調査において、地元関係者ヒアリングを踏まえ、将来の水質、植生への影響予測結果から考えられる適応オプションは、次の通りである。
| 適応オプション | 想定される実施主体 | 評価結果 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現状 | 実現可能性 | 効果 | ||||||||||
| 行政 | 事業者 | 個人 | 普及状況 | 課題 | 人的側面 | 物的側面 | コスト面 | 情報面 | 効果発現までの時間 | 期待される効果の程度 | ||
| 1.流入負荷削減施策 | 減肥料対策 | ● | ● 農家含む |
普及が進んでいない | ・周辺の農家は減肥料の意識は低い。 | △ | ◎ | △ | ◎ | 長期 | 中 | |
| 佐潟へ直接流入防止のため、側溝設置 | ● | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | △ | 短期 | 中 | |
| 2.水質改善のための底泥対策 | 浚渫 | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 下流への排泥 | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | △ | 短期 | 中 | ||
| 潟普請 | ● | ● NPO 含む |
普及が進んでいる |
|
△ | ○ | ◎ | ◎ | 長期 | 低 | ||
| かいぼり | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 高 | ||
| 3.地下水涵養 (浸透桝設置も含む) |
● | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 低 | |
| 4.水位管理の見直し | ● | ● | 普及が進んでいない |
|
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 短期 | 高 | ||
| 5.希少植物の移植 (系統維持) |
域外保全 | ● | 普及が進んでいない |
|
◎ | ○ | △ | ◎ | 短期 | 中 | ||
| 域内保全 | ● | 一部普及が進んでいる |
|
◎ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 中 | |||
| 6.モニタリング調査 | ● | ● | ● | 一部 普及が進んでいる |
|
△ | ○ | △ | ◎ | 長期 | 低 | |
| 7.潟の歴史、文化、自然を啓発する活動 | ● | ● | 普及が進んでいる |
|
△ | ◎ | ◎ | ◎ | 長期 | 低 | ||
| 適応オプション | 適応オプションの考え方と出典 | |
|---|---|---|
| 1.流入負荷削減施策 | 減肥料対策 | 既往の取組み。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」にある「環境保全型農業の推進」のなかで、「適正な施肥及び環境保全型農業を推進する」としている。 |
| 佐潟へ直接流入防止のため、側溝設置 | 周辺の畑地から直接流入を防ぐために、佐潟の潟端に側溝を掘って別の場所に逃がすという考え方。 地元環境団体からの提案事項。 |
|
| 2.水質改善のための底泥対策 | 浚渫 | 既往の取組み。佐潟の水質改善の一手段として、2014,2015 年度(平成26,27 年度)の2 ヵ年で,浚渫延長340m(幅6m、深さ約1m)、2,050m3 のドロを浚渫した。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 |
| 下流への排泥 | 既往の取組み。2016 年度(平成28 年度)から水門に付随する「ドロばき」を開門し、ドロの排出状況調査を行った。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 その後もドロの排出の試行を継続している。 | |
| 潟普請 | 既往の取組み。「佐潟クリーンアップ実行委員会」が実施主体となり、春の佐潟周辺のクリーンアップ活動と秋の観察舎脇の「ヨシ刈り」、佐潟橋付近の「ドロ揚げ」の計2 回を毎年実施。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 | |
| かいぼり | かつて、各地のため池などで冬の間、維持管理のために水を抜いて干し上げる管理がされていた。 近年、その水質改善効果、外来種駆除効果などが見直され、各地の池や湖で実施されるようになってきている。 |
|
| 3.地下水涵養 (浸透桝設置も含む) |
将来的に湧水量の変動幅が大きくなることに備えるためには、地下水の涵養が重要と考えられる。 | |
| 4.水位管理の見直し | 水位管理見直しの必要性は地元でも認識されており、「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」で今後の取組みとして挙げられている。 | |
| 5.希少植物の移植 (系統維持) |
域外保全 | 本来の生育環境での生育が難しくなった場合、遺伝子保存の観点から講じる手段である。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 |
| 域内保全 | 既往の取組み。佐潟公園内にある自然生態観察園において一部の希少種を保全している。 今後、自然生態観察園のさらなる活用や、域内の他の場所での保全も考えられる。 |
|
| 6.モニタリング調査 | 水質調査などは既往の取組みである。さらに、環境を把握するために必要な調査項目を検討する必要がある。 「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 |
|
| 7.潟の歴史、文化、自然を啓発する活動 | 既往の取組み。「第4期佐潟周辺自然環境保全計画(2019年4月)」 ワイズユースの考え方のさらなる普及、大学との連携、学校の総合学習での広がりなど、より充実させることが期待される。 |
|