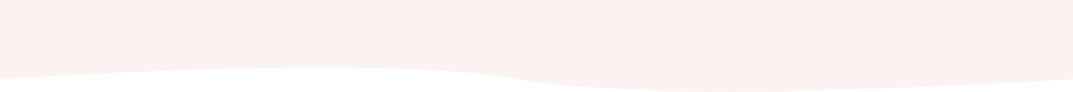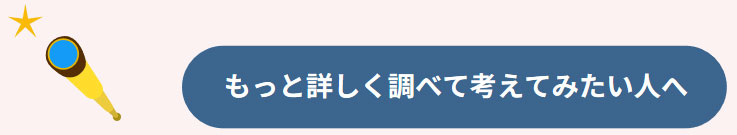「釣った魚で食中毒になった。」
- 南からやってくる生き物たち -
このお話は近年、本州沿岸の魚でも報告されるようになったシガテラ毒による食中毒をもとにしています。シガテラ食中毒は昔から熱帯・亜熱帯ではよく知られており、日本でも沖縄では発生件数が多いため一般に良く認知されているのですが、本州ではまだほとんどの人が警戒していません。
シガテラ毒は、熱帯・亜熱帯海域に多く生息する植物性プランクトンの一種である渦鞭毛藻の Gambierdiscus toxicus などがもつことが知られており、これが付着した海藻を小魚が食べると、食物連鎖を通してより大きな肉食魚に毒が蓄積されることがあります。たまたまこの毒を持った魚を知らずに食べた場合、致死性は低いとされてはいますが、消化器・神経系の症状に苦しめられることになります。
食中毒の発生は本州中部以南に棲息するバラハタ、イッテンフエダイ、バラフエダイ、イシガキダイなどに集中しており、また都道府県ごとに中毒事例のある有毒種を中心に食用にしないように指導がされています。手っ取り早い自衛の方法は、お店などに流通している魚を食べることです。また釣りを楽しんでいる方は、普段からこういった情報に注意して、食中毒の知識を身に付けておくことが大事です。(詳しくは下に挙げた参考文献やwebサイトなどをご覧ください。)今後も海水温の上昇とともに、南方の海域に生息していたプランクトンや魚介類などの生き物たちが、本州の沿岸域にもますます広がってくるのではないかと懸念されています。
魚介類のみならず、山菜や木の実やきのこなど、私たちは昔から身の回りの自然の恩恵を受けてきました。しかし、それらが自分たちにとって害がないかどうかの判断は、その地域に棲息する動植物に向き合ってきた先人たちの経験則に基づいていました。
今後温暖化が進み、今までそこになかった南方の動植物が広がれば、地域ごとに昔から培われてきた経験則は更新を迫られるでしょう。
私たちよりも南の地域で暮らす人々が、昔から自然と向き合う時に気を付けてきたこと、自然と戦ってきた経験の中にも、今後温暖化した気候に適応するための術が見つかるかもしれませんね。
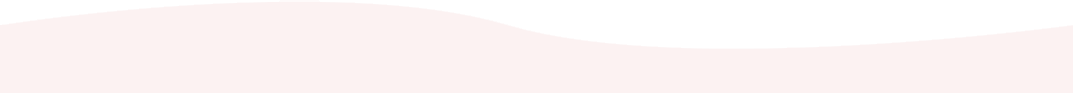
(雑誌)
(ウェブサイト)
- 沖縄県. ”シガテラ”. 沖縄県.2024.
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kurashikankyo/shoku/1004101/1018584/1004114.html,(参照 2024-04-18) - 神奈川県. ”情報誌「かながわの食品衛生」vol.19 釣った魚に毒があるかも?~シガテラ毒にご用心~”. 神奈川県. 2015.
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/e8z/cnt/f6576/p1010000.html,(参照 2024-04-18) - 厚生労働省.“自然毒のリスクプロファイル:魚類:シガテラ毒”. 厚生労働省. 2023.
https://www.mhlw.go.jp/topics/syokuchu/poison/animal_det_02.html,(参照 2024-04-18) - 松浦啓一. ” マリントキシン-毒を持つ魚介類に注意!-”. 国立科学博物館ホームページ ホットニュース. 2008.
https://www.kahaku.go.jp/userguide/hotnews/theme.php?id=0001391489624495,(参照 2024-04-18)