計画策定ガイドマップ
地域の担当者用このページは官公庁・自治体職員や研究者向けの情報です
地域気候変動適応計画の策定と改定について、地域気候変動適応計画策定マニュアル(以下、マニュアル)のSTEP1~8までの手順ごとに、参考資料、お役立ちツール等を紹介します。なお、計画策定マニュアルのページでは、マニュアル本編を提供しているので適宜ご参照ください。
各STEPにおいて、アンケート調査を実施する際には以下のページを参考にしていただけます。
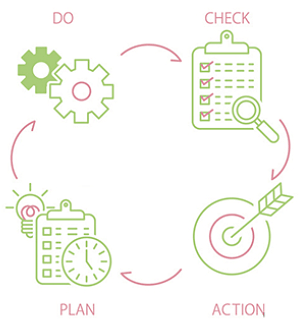
地域適応計画を策定/変更するための手順を以下の図の通り想定し、それぞれのSTEPにおける作業や参考情報について説明しています。水色で示すSTEPは主幹部局(環境部局など)が中心となって実施、オレンジ色で示すSTEPは主に気候変動影響が生じている関連部局と主幹部局が協力して実施することを想定しています。
主幹部局が中心
地域気候変動適応計画策定/改定に向けた準備
- 気候変動への適応の方針や目標の検討/見直し
- 地域適応計画の形式の検討/見直し
- 計画期間の設定/見直し
- 基礎情報(地理的条件、社会経済状況等)の整理/更新
- 区域の気候・気象(気温や降水量など)の特徴の整理/更新
主幹部局と関連部局
影響評価の実施
各分野の気候変動影響について評価を実施し、地方公共団体において優先度の高い分野や項目を特定
主幹部局と関連部局
既存施策の気候変動影響への対応力の整理
地方公共団体における優先度の高い気候変動影響を対象に、それそれに関連する既存施策の情報を収集し、将来の影響に対する対応力を整理
主幹部局が中心
適応策の取りまとめと地域気候変動適応計画の策定
STEP1~STEP6で整理した情報を取りまとめ、地域適応計画を策定
主幹部局が中心
地域気候変動適応計画の進捗状況の確認
地域適応計画に取りまとめた適応策の実施状況を確認
STEP1地域気候変動適応計画策定/改定に向けた準備
STEP2これまでの気候変動影響の整理
STEP3将来の気候変動影響の整理
STEP6適応策の検討
-
国や地方公共団体、事業者、あるいは国民が、気候変動緩和・適応策や影響評価の基盤情報として使えるよう、日本及びその周辺における大気中の温室効果ガスの状況や気候システムを構成する諸要素(気温や降水、海面水位・水温など)について、観測事実と将来予測をとりまとめた報告書。
将来の気候は、主に2°C/4°C上昇シナリオ(RCP2.6/8.5)に基づき予測している。本編と詳細版の2種類があり、本編は国や地方公共団体等で気候変動対策に携わる担当者向け、詳細版は専門家(研究者)や、研究者以外のより詳細な情報を参照したい読者の利用が想定されている。(出典:文部科学省、気象庁) -
各分野における気候変動影響の概要に加えて、気温や降水量などの観測結果と将来予測、影響の評価に関する今後の課題や現在の政府の取組をとりまとめた報告書。参考資料として、各分野における気候変動影響に関する詳細な情報をまとめた「気候変動影響評価報告書(詳細)」も提供されている。
気候変動適応法第10条に基づき、中央環境審議会における審議及び関係行政機関との協議を経て、環境省が作成した。2015年の中央環境審議会による意見具申から5年後の2020年に取りまとめられた2回目の気候変動影響評価で、気候変動適応法に基づく影響評価としては初めてのものとなる。(出典:環境省) -
平成30年に11月に閣議決定された「気候変動適応計画」に記載のある主要7分野を掲載。(出典:国立環境研究所(A-PLAT))
-
平成29年度より3カ年の計画で実施する環境省・農林水産省・国土交通省の連携事業。全国及び6地域で実施される事業の概要や、気候変動影響に関する調査の内容等を掲載している。(出典:環境省)
-
気候、影響に関するマップやグラフ、適応に関する施策情報をご覧になれます。(出典:国立環境研究所(A-PLAT))
-
地方公共団体の適応に関連する計画(※適応に関する記載のある環境関係の計画等)や情報を掲載している。(出典:国立環境研究所(A-PLAT))
-
国立環境研究所が作成する適応策の事例集。全国及び世界の適応ケーススタディー等を適応各分野別にチェックできる。随時更新中。(出典:国立環境研究所(A-PLAT))
-
気候変動に関する適応策の推進に向けた科学的知見についての報告書。気候変動に関する政府間パネル第5次評価報告書の内容、定常観測の結果、政府の研究プロジェクトの成果を基にまとめられている。内容は気候変動の要因・メカニズム、気候変動の観測結果と将来予測、気候変動がもたらす日本への影響である。(出典:環境省、文部科学省、農林水産省、国土交通省、気象庁)
-
日本と世界の気候・海洋・大気環境の観測・監視結果に基づいて、気候変動に関する科学的な情報・知見をまとめた報告書。世界各地の異常高温や豪雨、熱帯低気圧による甚大な被害、日本では、沖縄・奄美の統計開始以来最高を記録した8月、9月の月平均気温、7月の九州北部豪雨、東海地方の高潮・高波被害などが報告されている。(出典:気象庁)
-
20世紀末と21世紀末の間の日本付近における気候変動予測に関する報告書。ここでは、現時点を超える政策的な緩和策が行われないことを想定(IPCC第5次評価報告書、RCP8.5シナリオ)した計算に基づいている。また、いくつかの現実的な毎面水温上昇パターンの条件下で気候変動の不確実性が計算される。(出典:気象庁)
-
日本国内の各都道府県内の観測点で記録された気象データをcsvファイルでダウンロードするためのウェブサイト。データ項目は、気温、降水量、日照/日射、積雪/降雪、風速、湿度/気圧、雲量/天気。観測期間を任意に設定でき、多様な表示オプションを選択できる。(出典:気象庁)
-
日本の各地方、各都道府県における気候の変化に関するリンク集。日本付近の大まかな変化傾向が掲載されている次の情報を参照したうえでの利用を推奨している。「地球温暖化予測情報第8巻」(気象庁、2013)及び「地球温暖化予測情報第9巻」、(気象庁、2017)(出典:気象庁)
-
適応計画に向けた日本周辺の将来の気候予測計算の結果をまとめたもの。予測項目は気温、降水、積雪・降雪であり、IPCC第5次評価報告書に記載されている複数の将来シナリオに基づいて2080~2100の計算が実施されている。それぞれのシナリオに応じた計算結果をもとに将来気候の不確実性の幅が評価される。(出典:環境省、気象庁)
-
都道府県や産地等が適応策に取り組む判断をするための情報を平成28年度と平成29年度に度農林水産省がまとめたもの。29年度では、日本を9つの地域に区分し、各地域の品目・項目について気候変動の影響、将来展望、適応策オプション、取り組み事例が記載されている。28年度は関東・東海地域の情報である。(出典:農林水産省)
-
詳細版と概要版が掲載されている。詳細版では総論の後、分野・品目別対策が農業、森林・林業、水産資源・漁業・漁港等に関して述べられている。また、分野共通項目として温暖化予測、技術開発、地域への展開、農林水産事業者の熱中症、鳥獣害、食糧需給予測、国際協力などが取り上げられている。(出典:農林水産省)
-
地球温暖化の影響と考えられる農業生産現場での高温障害等の影響、その適応策等を都道府県毎に農林水産省が取りまとめたもの。普及指導員や行政関係者の参考資料として適している。現時点で必ずしも地球温暖化の影響と断定できないものも、将来の温暖化進行を考慮して取り上げられている。(出典:農林水産省)
-
国土交通省が推進すべき適応の理念及び基本的な考え方が示された後、気候変動に伴う影響を自然災害分野、水資源・水環境分野、国民生活・都市生活分野、産業・経済活動分野、その他の分野に分類し、適応に関する施策が提示されている。(出典:国土交通省)
-
気候変動の生態系への影響について具体的に紹介された後に、以下の3つの視点から適応策がまとめられている。1.気候変動が生物多様性に与える悪影響を低減するための自然生態系分野の適応策。2.他分野の適応策が行われることによる生物多様性への影響の回避。3.気候変動に適応する際の戦略の一部として生態系の活用。(出典:環境省)
-
中央環境審議会が政府全体の適応計画策定に向けて、気候変動の日本への影響と今後の課題を取りまとめた平成27年の報告書。気候変動が日本に与える影響の程度、影響の発現時期、適応の着手・意思決定が必要な時期、情報の確からしさ等を科学的観点から取りまとめている。(出典:中央環境審議会)
-
中央環境審議会「日本における気候変動による影響の評価に関する報告と今後の課題について(意見具申)」をはじめとする気候変動の影響評価に関する文献を分野ごとに紹介している。(出典:国立環境研究所(A-PLAT))
-
日本における気候変動による影響の評価について取りまとめた報告書。特に、重大性、緊急性、確信度の観点を導入し、重大性は社会、経済、環境の3つの観点から、緊急性は影響の発現時期、適応の着手・重要な意思決定が必要な時期の2つの観点から、確信度はIPCC第5次評価報告書の考え方を準用して、それぞれ評価されている。(出典:中央環境審議会 地球環境部会、気候変動影響評価等小委員会)
-
環境省環境研究総合推進費S-8の4年間(平成22~25年度)の成果報告書。分野別影響と適応策の課題が水資源、沿岸・防災、生態系、農業、健康の5つの課題、被害の経済的評価、温暖化ダウンスケーラ、自治体の適応策の実践、九州の温暖化影響と適応策、アジアから見た適応策の在り方、総合影響評価と適応策の効果がそれぞれ1つの課題として報告されている。(出典:環境省)
-
S-14 気候変動の緩和策と適応策の統合的戦略研究統合的戦略研究S14のウェブサイト。研究概要、参加メンバー、研究業績となる成果、会合報告、関連資料、リンク集などが掲載されている。(出典:環境省)
-
SI-CAT 気候変動適応技術社会実装プログラム日本全国の地方自治体等が行う気候変動対応策の検討・策定に向けたSI-CATの役割をSI-CATを構成する4つのコンポーネント、社会実装機関、技術開発機関、モデル自治体、ニーズ自治体に関してまとめられているウェブサイト。(出典:文科省)
-
関係府省庁連絡会議によってまとめられた気候変動の影響への適応計画の進捗管理についての報告書。適応計画に掲げられた各施策が56の施策群に整理され、各府省庁が対象となる施策についてまとめている。(出典:気候変動の影響への適応に関する関係府省庁連絡会議)
-
環境省「平成27年度地方公共団体における気候変動影響評価・適応計画策定等支援事業に」参加した11団体の取組事例を紹介している。
以下、関連リンクhttps://www.env.go.jp/press/100971.html(出典:環境省)